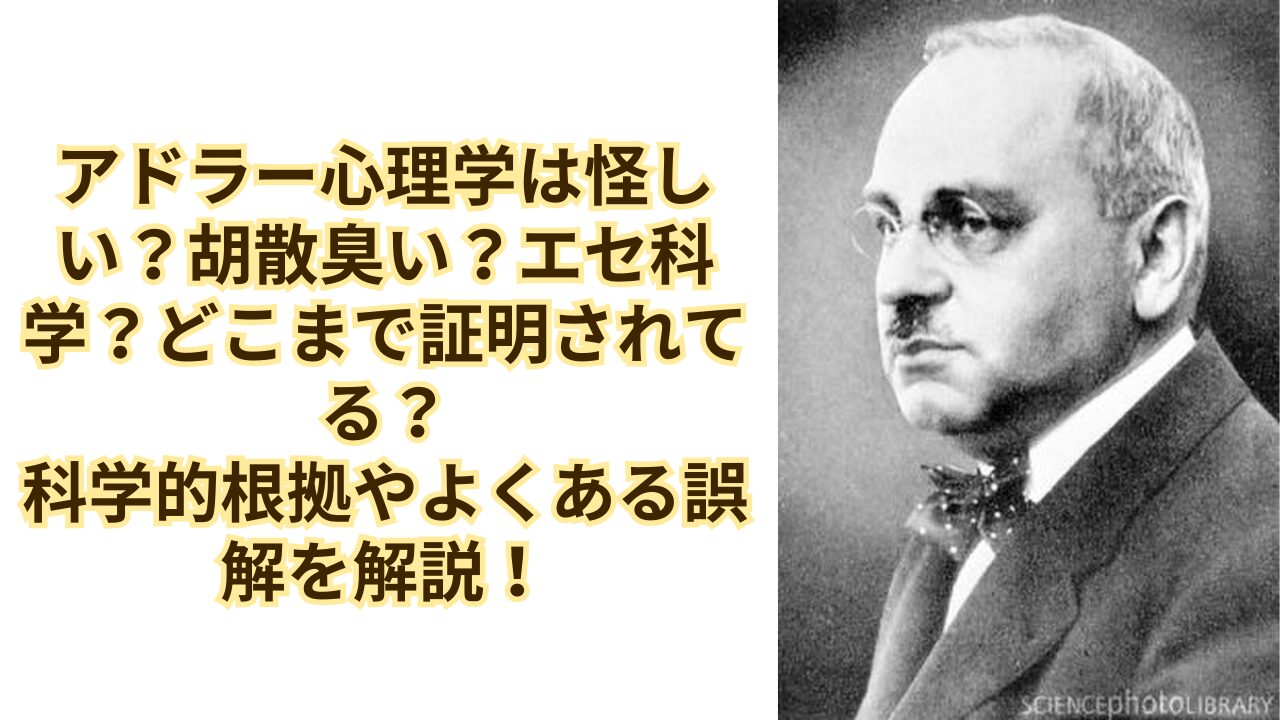アドラー心理学を一言でまとめるなら、「自分の人生を自分で選び(自己決定性)、目的に沿って行動し(目的論)、余計な他者コントロールを手放す(課題の分離)ことで、他者と協力して生きる力(共同体感覚)を育てる心理学」と言えます。
しかし、彼の心理学は多くの自己啓発本の中に埋もれており、やや胡散臭いと感じてしまう人は少なくないかもしれません。実際後世でも埋もれてしまい同じことを言っていても引用されていない傾向にあります。
確かにアドラーの考えは科学的な検証の積み重ねというよりも、自分の臨床経験を総合した考えであり、また事実だけでなく「どのように生きるべきか?」という科学の範疇を超えたこともテーマにしており、どちらかというと哲学に近いという側面もあります。その意味で科学ではないという意見もあります。
そこでアドラー派の基本的な事実関係に関する概念がどれほど進化生物学・心理学・行動経済学・神経科学・脳科学的に受け入れられているかについて本記事では考えていきます。Miller & Dillman(2016)をベースに論文を追加しています。Miller & Dillman(2016)で紹介されている論文の引用は省略します。
結論から言うと概ね方向性は同じと言えますが、葛藤と自由意志に関する考えには部分的に相違があります。
アドラーとアドラー心理学について
アルフレッド・アドラーは1870年に生まれ、1937年に亡くなった心理学者で、彼が生きた時代の心理学の主流は「人間の行動は、過去の原因(幼少期の体験・トラウマ・生理的要因など)によって決まる」という考えに基づいていました。
たとえばフロイトは「無意識の欲望」や「性的衝動」などを原因として重視していました。また、精神医学も「症状を記録し、因果関係を分類する」スタイルで、まさに「事実の積み重ね」に終始していました。アドラーは医師として患者と接するうちに、この「原因説明主義」に大きな疑問を感じるようになります。これが「原因論」と呼ばれるものです。
それに対してアドラーは疑問を持つようになります。若い頃は眼科医・内科医として出発し、肺疾患や結核の患者を多く診ていました。彼はあるとき、同じ病気でも患者によって回復の度合いがまるで違うことに気づきます。「同じ病気なのに、なぜ「生きようとする意欲」がある人だけが回復するのか?」これを単なる「身体の違い」では説明できないと考えたことが、アドラーの第一の転機となりました。つまり、「人は受け身の存在ではなく、自らの生き方を選んでいるのではないか?」という発想が芽生えたのです。これが「目的論」と呼ばれるものです。
アドラーは精神科医になった後、感情や行動に関しても同様であるとこの考えを発展させ、フロイトと袂を分かち、現在のアドラー心理学である「個人心理学」を創設します。
アドラー心理学は自分の人生や個性を重視した上で、その能力を活かして社会との繋がりを模索することを提唱している点が非常に先進的で、現代の個人の幸福だけを追求する欧米的観念や、「出る杭は打たれる」日本的観念のような極端な思考を手放す上で、紀元前6世紀の北インドのガウタマ・シッダールタ(仏陀・釈迦)の原始仏教や、紀元前3世紀初めの古代ギリシャでゼノンによって始まり古代ギリシャとローマで広まったストア哲学(ストア派)に並んで、とても重要な心理学・哲学だと私は考えています。
「共同体感覚」に科学的根拠はある?
アドラー心理学の中核となる信条の一つとして、個人には生来の社会的な関心の能力があるという考えがあります。
これはアドラー心理学では「共同体感覚(Social Interest)」と呼ばれ、家族・地域・職場など、自分が社会の一員であると感じ、他者とつながり、貢献しようとする感覚を表しています。この規模感は家族から地球規模まで様々です。
端的に言うとこの共同体感覚の欠如、つまり「自分は様々なスケールでの所属コミュニティに貢献できている!」という感覚の不足が不安感・不幸感・孤立感・劣等コンプレックス・自己中心的な行動に大きく関係しているという主張がアドラー心理学にはあります。
これは神経科学の研究でも共同体感覚が重要であることは示されているのでしょうか?
このような考え方は幸福に関する多くの神経生物学的見解と一致しており、『A Counselor’s Introduction to Neuroscience』という教科書でも同様のことが記載されており(McHenry et al., 2014)、思いやりと優しさを表現することが人間関係や心身の健康を強化する可能性があることがいくつかの研究で示唆されています(Fredrickson et al., 2013; Poulin & Holman, 2013)。
オキシトシンは視床下部で合成され下垂体後葉から分泌されるホルモンで、「愛情ホルモン」とも呼ばれ、社会的な絆を感じたり、誰かの世話をすることによって分泌されます。
このオキシトシンは共同体感覚をもつことによる幸福感をもたらす根源であると考えられますが、このオキシトシンの分泌は単にそれだけではなく、ストレスによって誘発された生理学的損傷の修復も行うことが分かってきています。
Poulin & Holman(2013)の研究では向社会的な行動をとった人は内因性オキシトシンのレベルが高く、ストレスの負の症状が少ないことを発見しています。著者らは、人が向社会的な行動をとることは、オキシトシンの放出を刺激し、ストレスの負の影響を和らげる可能性のある方法であると示唆し、オキシトシンがストレスが健康に及ぼす悪影響を緩和することを示しました。
また別の Fredrickson et al.(2013)の研究では、より高い目的を持ち、コミュニティとつながり、他者に奉仕していると報告した人は、炎症マーカーのレベルが低く、それに対して、快楽的幸福の経験が多いと報告した人は、炎症誘発性遺伝子のレベルが上昇し、抗ウイルス反応のレベルが低下したことが報告されています。
アリストテレスは快楽・満足感・ポジティブな感情といった、短期的な喜びを追求する幸福である「ヘドニア」と、人生に意味や目的を見出し、短期ではなく長期的な充足感を得る幸福である「ユーダイモニア」を区別しましたが、ここでは社会的にユーダイモニアを見出した人がより健康度が高かったと解釈されています。
これらの知見は、「コミュニティ意識」を強く持ち、他者の幸せに貢献すること自体が自分にとっても精神的な安定や身体的な健康に大きなメリットがあるということを生理学・神経学的に示していると言えるでしょう。
アドラーはダーウィンの進化論にも言及しており、他の動物が身体的な強さを進化させたのに対して、ヒトは社会的集団を形成することで環境に適応したのであり、そのことが共同体感覚を持つことの重要性と繋がっていると考えていました(アドラー・岩井,2024)。
この考えは現在の進化生物学の観点から言っても社会脳仮説(social brain hypothesis)などの形で提唱され、おおよそ合っていると言えます(Pedersen et al., 2014; Dunbar, 2024)。
「アドラー流の対人関係」に科学的根拠はある?
アドラー流の対人関係では課題の分離(Separation of tasks、他者と自己のやるべきことを明確に線引し自分の課題に集中し他者の課題に対しては求められるまで手を出さない考え方)を徹底的し、「縦の関係(上下関係)」を否定し、「横の関係(対等な関係)」を重視し、勇気づけ(困難に直面した人がそれを乗り越えるための活力や自分にはできるという自信を与えること)を行うことが推奨されます。
これは現代では行動療法に起源を持つ「アサーティブネス(assertiveness、自他を尊重した自己主張)」に一部類似しています。
アサーティブネスは自分と相手を尊重し、自分の意見や要求、感情を率直に、誠実に、対等に表現するコミュニケーション手法・態度のことで、アドラー流の対人関係とは直接的な言い回しを推奨する点(「察しの文化」の否定)と対等性を強調する点が一致しています。
アドラー流の対人関係自体は科学的検証は不足していますが、アサーティブネスに関しては不安・ストレス・抑うつ感を軽減することがいくつかの研究で示されています(Cantero-Sánchez, 2021; ElBarazi et al., 2024)。
また原始仏教・ストア哲学・原始キリスト教でも自分を守りつつ、共同体で慈悲を持って相手のことも尊重するという点において同様の思想が目立ちます(Bazzano, 2005; Goerger, 2017; Case, 2024)。
「幼少期の経験の特異性」に科学的根拠はある?
アドラー心理学では幼少期の経験は、個人の自己・他者・世界に対する見方の全体的な発達に極めて重要だと考えています(Adler, 1956)。
アドラー(1956)は、個人は特定の傾向を持って生まれるものの、特定の特性や才能の発現はコミュニティ(周りの環境)に原因があると主張しました。
つまりこれは「子供の頃の経験は大人の頃の経験より質的に重要で、「ライフスタイル」の確立に深く関与している」という考えとも言い換えられます。
ここでいうアドラー心理学の「ライフスタイル(Lifestyle)」とは幼少期経験と所属欲求が融合した、個人が人生を生きる上で持つ独自の「無意識の設計図」のことで、自己概念(私は~だ)、世界像(世界は~だ)、自己理想(私は~でありたい)という3つの要素から構成されます。
そのため、アドラー心理学派のカウンセラーは文化的および家族的価値観・性役割の期待・生家内の人間関係の性質・心理的な出生順序など、個人の家族構成を深く洞察することでその人の内面を知ろうとします。
神経科学的にはどうなのでしょうか?
現在の脳発達モデルは幼少期の経験が個人の自己・他者・世界に対する意識に大きな影響を与えると考えており、幼少期の経験に関するアドラーの見解を補完していると考えられます(Andersen et al., 2008; McHenry et al., 2014; Perry, 2009; Siegel, 2012)。
脳は、子宮内で脳幹から始まり、成人初期にかけて前頭前皮質へと続いていく順序で発達します。神経学者たちは、メンタルヘルスに関する議論において重要な要素である脳の調節回路に関連する基礎構造は、主に生後5年間で形成されると考えています(Andersen et al., 2008; Perry, 2009)。
その過程で、子供は幼少期に最も近かった養育者の神経回路を内面化することがしばしばあります。個人は特定の遺伝的傾向を持って生まれますが、環境的経験は、「エピジェネティクス」と呼ばれるプロセスを通じて、どの遺伝的傾向が発現または抑制されるかを大きく左右します(Garrett, 2011; Siegel, 2012)。
エピジェネティクスとはDNAの塩基配列自体を変えずに、遺伝子の働き(発現)を制御する仕組みのことで、生物学の初学者の人や古い生物学の考えのままの人は「環境による制約はあるものの、遺伝子によってとる行動はガッチリ決まっている」と考えてしまいがちですが、エピジェネティクスの作用によって「どちらにもなりうる可能性を両方持っていて、環境によって特定の遺伝子が発現して行動が出ることがある」ということが証明されているのが現在の生物学です。
つまり受け継がれた直接の遺伝子だけでなく、幼少期の環境が遺伝的な発現に関与し、その後の人生で良い影響や悪影響が出ることがあるということです。
例えば、Fallon(2013)は、暴力的な精神病理学的行動に従事した個人を脳スキャンで検証しました。すると参加者が「前頭葉と側頭葉の特定の部分、つまり自制心と共感に一般的に関連する領域における脳機能の低下」という類似した神経活動プロファイルとパターンを共有していることを発見しました。
ここまでは脳の異常によって共同体感覚を失っている状態であると言えるでしょう。ある意味普通ではあります。
ところがさらに調査を進めると、養育環境が悪いことが原因で、攻撃性の高さや共感性の低さを示さずに、精神病質傾向を持つ個人と類似した神経活動プロファイルを持つ個人が存在することが示唆されているのです。
つまりアドラーが推測したように、幼少期の経験が遺伝的傾向に影響を与えるという可能性を示唆しています。
これはスラム街で生まれた子供が親や周りの人間の影響で悪いとも思わず、犯罪を犯したりギャングに入ったりする事例や毒親の子供が毒親になってしまう事例を考えても実際の感覚に非常に近いものがあります。
また、アドラーの考えは別の心理学の概念である「愛着理論(attachment theory)」とよく一致しており、ほとんど言い換えと言っても過言ではありません。
愛着理論は心理学者のジョン・ボウルビィが1960年代から1970年代の研究で提唱した、人間が他者との間に築く感情的な絆(愛着)が、その後の心の健康や対人関係に大きな影響を与えるという理論です。
愛着理論はフロイトが説明するように母子関係は子供側が「おっぱいをくれた人だから(欲求充足)」という学習によって成立するものではなく、他のサルなどと同様に本能的・先天的に子供が親を求めるメカニズムによるものということを示した点で画期的でした。
しかし、少し前のアドラーが直接参照されることなく、臨床での観察・比較研究・動物行動学の参照によってこの理論を完成させています。
この愛着理論は古いものではありますが現代でも広く受け入れられ、多くの神経科学研究者たちも、愛着は暗黙記憶として内面化され、安全な愛着は感情の調整・恐怖の調整・調和・洞察・自己理解・共感・道徳性を促進する神経構造と関連し(Schore & Schore, 2008; Siegel, 2012)、不安定な愛着は、感情的・社会的知能・実行機能。ストレス調節能力の低下と関連している(Perry, 2009)ということを示しています。
以上のように幼少期の経験を強調したアドラーの考えは用語を変えながらも現在でも支持されていると言えます。
「目的論」や「人生の嘘」は正しい?
目的論とは「人間の行動は、過去の原因(幼少期の体験・トラウマ・生理的要因など)によって決まる」という原因論に対して、「人は何らかの目的に向かって今その行動や感情を選んでおり、過去の原因として挙げられるものは目的に合わせて都合よく持ってきているに過ぎない」という考えです。
教科書ではこの程度でしか書かれないので勘違いされやすい部分ですが、そうはいってもアドラーは遺伝子や過去が現在の状況の原因になっていること自体は否定していません(アドラー・岩井,2024)。
ただ、その原因を選び出しているのは本人の都合であると言っているのです。
「お金がなく顔が良くないから結婚できない」という話はよく聞きますが、お金がなくて顔が良くなくても結婚している人が世界中にたくさんいるという反例を考えれば、そういう傾向があったとしてもそれが全ての原因とするのは間違いであることは明らかですが、往々にしてこのような表現は見られます。
虐待をされても非行になる原因にはなりえますが、非行に走らずに大成する人もいます。
このように建設的な方向か、非建設的な方向に動くかは自分で選べるとアドラーは解いてるのです。アドラーはもっともらしい理由をつけて行動しないことを「人生の嘘(Life Lie)」と呼びました。
目的論や人生の嘘の概念の正しさ、つまり原因論の間違い自体には例外を出すだけで簡単に証明できると思います。
そうすると、なぜ脳は本当は行動しなければならないのに言い訳をして「人生の嘘」をついてしまうのでしょうか?
このことは現代的にいうと「不安(anxiety)」による「先延ばし(procrastination)」行動への「認知的不協和(cognitive dissonance、心の中に矛盾する考えや行動が同時に存在することで生じる心理的な不快感)」の解消のための「自己欺瞞(self-deception、自分で自分の心をだますことで自分の良心や真実を知りながらそれを自分自身に対して無理に正当化したり目をそむけたりする心理作用)」であると考えられます。
人間はたしかに現状維持によって危害や潜在的な脅威を避けることで幸福と生存が得られる場合もありますが、現状維持がマイナスの結果につながることもあります(Yamamori et al., 2023)。
たとえば、就職面接をするとき、新しい仕事を得るというメリットと、面接での失敗したり恥ずかしさを経験するリスクを比較検討する必要があります。ただ、1 回の面接を断っても人生にほとんど影響がないですが、全て就職面接を日常的に避けていると、長期的には明らかに問題が生じてきます。
このように短期のリスクのために長期のメリットを回避する状況で一貫して回避することは、心理学では「先延ばし(procrastination)」、行動経済学では「現在バイアス(present bias)」と呼ばれ、本当は真面目にやっていれば得られたはず失われた報酬の合計が蓄積されるにつれて、ますますマイナスの影響をもたらし、最終的には人生で重要なことを見逃すことにつながります。
これは人間は生存が進化の過程で生存しているか分からない将来のメリットについて過小評価し(時間割引)、現在被りうるリスクを過大評価する傾向にあるためであると進化生物学や行動経済学でも指摘されています(Rogers, 1994; 友野,2006)。
また、このような不安のプロセスは神経科学的には、海馬・扁桃体と前頭前皮質の結合が強まりすぎる(θ波同期が過剰化する)ことで、VIP+ニューロン・PV+ニューロン・SST+ニューロンのような介在ニューロンが過剰に働くことがマウスの実験では明らかになっています(Mack et al, 2023)。
つまり進化的に前頭前皮質の制御系の機能が強く働きすぎ、不安に支配されやすくなり、将来的な報酬(やりたいこと)よりも、現在の失敗やリスク(罰)を過大評価し、先延ばししてしまい、しかしデメリットも理解しているので認知的不協和が発生し、それを解消するために自己欺瞞として「人生の嘘」をつくという流れです。
これは不確実性が高く死が間近にあった古代においては行動を慎重にさせ、現状維持を促進させるという意味で非常に適応的な進化であると言えますが、技術が発達し行動のリスクが低くなった現代では適応的であると言えない状況にあります(Rogers, 1994; Rasmussen & Dover, 2006; Villmoare et al., 2024)。
原始仏教やストア哲学でも「妄想」や「執着」でリスクを過大評価することを戒めています(Ding et al., 2023)。原始キリスト教でも同様です。
「勇気」を持つ方法は正しい?
アドラーは「人生の嘘」を乗り越えるためには「勇気(courage)」が必要であると述べています。
アドラー心理学における「勇気」とは困難や課題に直面したときに、それを克服し、前向きに行動しようとする「活力」や「意欲」そのものを指します。
アドラーはその勇気を出す方法について自体はリスト化はしていませんが、趣旨を汲み取ると以下のような方法が考えられます。
- 小さな行動から始める
- 課題の分離で不要な不安を減らす
- 劣等感を成長の動機にする
- 他者貢献を意識する
- 自己決定性を強化する
このうち「小さな行動から始める」に関しては現代では「スモールウィン(Small Wins)」と呼ばれ、Weick(1984)によって再発見されています。
Small Wins は大きな目標達成に向けて日々積み重ねる、小さくても達成可能な適度な成功体験のことで、Weickは大きく複雑な問題を「手に届く小さな部分」に分けて、 Small Wins を積み重ねることで、勢い(モメンタム)や支持を得られ、変化が起きやすくなると論じています。
例えば勉強なら1日10分だけ単語を覚える、といったようなことです。
これによって達成による自己効力感を持つようになり、希望・信念・楽観主義・自信というポジティブな好循環が生まれるだけでなく、実践を通して学ぶことでより良い戦略のフィードバックに繋がります(Termeer & Dewulf, 2019)。
「大きなことをする計画を思考するよりとにかく少しでもやってみる」ということの重要性は現代でも強く支持されています。ソフトウェアの開発手法のアジャイル開発はその一例です。
一方、課題の分離が本当に不安解消に繋がるかは研究が不足していますが、感覚的には正しく思えます。
課題の分離とほとんど同じ考え方はストア哲学でも述べられています(Delaney, 2023)。
アドラー心理学に間違っている部分はある?
アドラー心理学の考え方が現在と大きく違うと思われるのは2点あると思います。
葛藤が存在しないというのは本当?
まずは葛藤の考え方です。アドラー心理学では意識と無意識との間に葛藤を認めません。これは全体論(holism)と呼ばれます。
これは「自分の中の自分と戦う」という考え方を否定し、内面的な葛藤は目的達成のためにあるという考えです。
これはあまり現代的にはこのような解釈がなされることは少なく、例えば進化心理学では心は統一体ではなく目的ごとに分裂した部分(モジュール)からなっていると説明されることが多いです。領域固有性(domain specificity)とも最近では呼ばれます(小田・大坪,2023)。
他にもポジティブ心理学で有名な社会心理学者ジョナサン・ハイトは「象と象使い」のメタファーを提示しています(Haidt, 2006)。「象と象使い」というメタファーは初期仏教経典『ダンマパダ(法句経)』でも使用しています。
「象」は意識とは切り離された部分で刺激に対する反応や快と不快を通じた動機の形成にかかわる心の部分を指し、「象使い」は意識と言語と合理的長期的判断にかかる部分を指します。
象は進化的により原始的に発達した延髄・小脳・中脳・間脳の要求であり、これが主役で、大脳皮質である象使いは脇役としてわずかに方向性をコントロールできるに過ぎないという考えです。実際には大脳皮質同士の対立も考えられます。
ただこれは解釈の問題で、象と象使いが一体となって何かしらの方向(目的)に向かって進むことは間違いなく、「象のせいで今日も苦しんでしまった」という建設的でない思考を防ぎ、たとえ象使いの役割が小さいとしても、それぞれの脳の部位からのメッセージをポジティブに受け止める意味では全体論的に人生を捉えるのは有益だと私は考えています。
自由意志は存在する?
次にアドラー心理学では自由意志が存在するという前提に立っています。だからこそ自分でより良い建設的な行動を選択できると考えているわけです。
一方で現代ではあらゆる人間の心理や行動はあらゆる環境要因と遺伝的要因によって規定されていると考える自由意志の不在論(決定論)が主流です。
ここについて哲学的に深く議論することもできるのかもしれませんが、アドラーはそういった哲学論争がしたいわけではなくあくまで自由意志が存在すると仮定し未来を変える努力を促したのだと考えられます。
心理学では実験的に試験者に反自由意志のメッセージを与えると「不正行為増加」・「攻撃性増大」・「援助低下」・「運動準備の低下」・「自己抑制の低下」などを報告する研究が複数あり、これは最近のメタアナリシス(メタ分析)研究では影響は低いとされましたが(Genschow et al., 2023)、限定的な状況ではありえるかもしれません。
そもそも、未来のことは初期値が不明なので正確な予測は不可能であり、未決定なので学ぶことで未来が変更可能であるという事実は、たとえ自由意志が存在しないとしても変わらないでしょう。
最後にアドラーの議論は100年ほど前の議論なので、幼少期発達モデルが不足しているなど、現代の水準で全ての人生について説明できていない側面はあります(Miller & Dillman, 2016)。この点は注意が必要です。
引用文献
アルフレッド゠アドラー・岩井俊憲. 2024. 超訳アドラーの言葉 エッセンシャル版. ディスカヴァー・トゥエンティワン, 東京. 229pp. ISBN: 9784799330104
Bazzano, M. 2005. To feel with the heart of another: Notes on Adler and Zen Buddhism. The Adlerian Year Book. pp.42-54. https://manubazzano.com/wp-content/uploads/2020/11/adler-and-buddhism.pdf
Cantero-Sánchez, F. J., León-Rubio, J. M., Vázquez-Morejón, R., & León-Pérez, J. M. 2021. Evaluation of an assertiveness training based on the social learning theory for occupational health, safety and environment practitioners. Sustainability 13(20): 11504. https://doi.org/10.3390/su132011504
Case, B. 2024. Love’s Limits in Paul of Tarsus and Seneca the Younger. Religions 15(10): 1169. https://doi.org/10.3390/rel15101169
Delaney, B. 2023. Reasons not to worry: how to be Stoic in chaotic times. Harper, 304pp. ISBN: 9780063314825 [=2024. 心穏やかに生きる哲学 ストア派に学ぶストレスフルな時代を生きる考え方. ディスカヴァー・トゥエンティワン, 東京. 421pp. ISBN: 9784799330784]
Ding, X., Ma, Y., Yu, F., & Abadal, L. M. 2023. The therapy of desire in times of crisis: lessons learned from Buddhism and Stoicism. Religions 14(2): 237. https://doi.org/10.3390/rel14020237
Dunbar, R. I. 2024. The social brain hypothesis–thirty years on. Annals of Human Biology 51(1): 2359920. https://doi.org/10.1080/03014460.2024.2359920
ElBarazi, A. S., Mohamed, F., Mabrok, M., Adel, A., Abouelkheir, A., Ayman, R., … & Mohamed, F. 2024. Efficiency of assertiveness training on the stress, anxiety, and depression levels of college students (Randomized control trial). Journal of Education and Health Promotion 13(1): 203. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_264_23
Genschow, O., Cracco, E., Schneider, J., Protzko, J., Wisniewski, D., Brass, M., & Schooler, J. W. 2023. Manipulating belief in free will and its downstream consequences: A meta-analysis. Personality and Social Psychology Review 27(1): 52-82. https://doi.org/10.1177/10888683221087527
Goerger, M. 2017. Moral Practice in Late Stoicism and Buddhist Meditation. Comparative Philosophy 8(1): 7. https://doi.org/10.31979/2151-6014(2017).080107
Haidt, J. 2006. The happiness hypothesis: finding modern truth in ancient wisdom. Basic books, New York. 320pp. ISBN: 9780465028023 [=2011. しあわせ仮説 古代の知恵と現代科学の知恵. 新曜社, 東京. 355pp. ISBN: 9784788512320]
Lavon, I., & Shifron, R. 2020. The use of early recollections in Adlerian psychotherapy: Evidence in neuroscience research. Psychology and Behavioral Science International Journal 15(2): 55590. http://dx.doi.org/10.19080/PBSIJ.2019.10.555908
Mack, N. R., Deng, S., Yang, S. S., Shu, Y., & Gao, W. J. 2023. Prefrontal cortical control of anxiety: Recent advances. The Neuroscientist 29(4): 488-505. https://doi.org/10.1177/10738584211069071
Miller, R., & Dillman Taylor, D. 2016. Does Adlerian theory stand the test of time?: Examining individual psychology from a neuroscience perspective. The Journal of Humanistic Counseling 55(2): 111-128. https://doi.org/10.1002/johc.12028, https://scholarworks.boisestate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1173&context=cifs_facpubs
小田亮・大坪庸介. 2023. 広がる!進化心理学. 朝倉書店, 東京. 183pp. ISBN: 9784254523065
Pedersen, C. A., Chang, S. W., & Williams, C. L. 2014. Evolutionary perspectives on the role of oxytocin in human social behavior, social cognition and psychopathology. Brain Research 1580: 1-7. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2014.07.033
Rasmussen, P. R., & Dover, G. J. 2006. The purposefulness of anxiety and depression: Adlerian and evolutionary views. The Journal of Individual Psychology 62(4): 366-396. ISSN: 1522-2527, https://psycnet.apa.org/record/2007-03417-003
Rogers, A. R. 1994. Evolution of time preference by natural selection. The American Economic Review 84(3): 460-481. https://www.jstor.org/stable/2118062
Termeer, C. J., & Dewulf, A. 2019. A small wins framework to overcome the evaluation paradox of governing wicked problems. Policy and Society 38(2): 298-314. https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1497933
友野典男. 2006. 行動経済学 経済は「感情」で動いている. 光文社, 東京. 397pp. ISBN: 9784334033545
Weick, K. E. 1984. Small wins: Redefining the scale of social problems. American Psychologist 39(1): 40-49. https://doi.org/10.1037/0003-066X.39.1.40
Villmoare, B., Klein, D., Liénard, P., & McHale, T. S. 2024. Evolutionary origins of temporal discounting: Modeling how time and uncertainty constrain optimal decision-making strategies across taxa. PloS one 19(11): e0310658. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0310658
Yamamori, Y., Robinson, O. J., & Roiser, J. P. 2023. Approach-avoidance reinforcement learning as a translational and computational model of anxiety-related avoidance. Elife 12: RP87720. https://doi.org/10.7554/eLife.87720.4