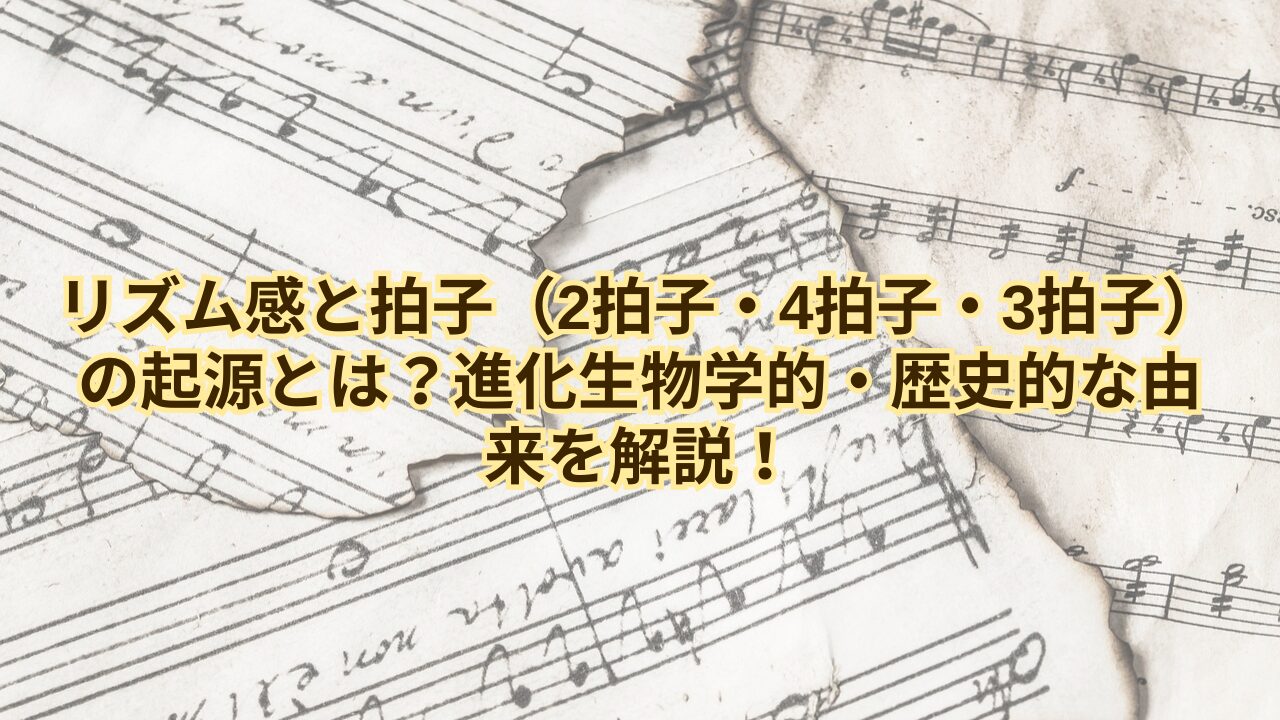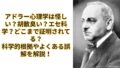音楽を聴いたり、歌を歌ったり、ダンスが趣味になると、自然とリズム感や拍子といったものに関心を持つようになっていきます。
しかしその起源は?と考えると答えられない部分が多いと思います。あまりにも自然にリズムにノッてしまうことが多いので疑問にも思わないかもしれませんが、このような能力を持っているのは実は生物の中でも非常に限られ、リズムを予測できるのはヒト固有と言ってしまっても良いほどの能力です。
そのリズムが心地よいと感じる根源には、明確な答えはまだ出ていませんが、一説には「歩行」が深く関与していると考えられており、更に拍子のうち2拍子と4拍子の起源でもあると考えられています。ただしきちんとした音楽理論に基づいた拍子の概念自体は中世後期のヨーロッパでバロック音楽が生まれてからです。
3拍子は特殊で広く用いられるになったのは16世紀のオーストリアのワルツであるとされ、回転を伴う動きにマッチしていたことから生まれたとされています。
本記事ではリズム感と拍子(2拍子・4拍子・3拍子)の起源について進化生物学的・歴史的に解説していきます。
リズム感覚の起源は?ビートを刻むのはヒトだけでない!?
リズム(律動)は「生物が知覚できる一定のパターンで繰り返される現象」のことです。
リズムをとる行動自体は昆虫からサルまで広く見られる現象で例えば以下のような例があります(Iversen, 2016)。
| 動物種 | 同期の特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| カエル類 | 鳴き声の同期(chorusing)。 | 繁殖行動に関連。オスのカエルが鳴き声を同期させることで合唱全体の信号強度を高め、鳴き声の場所をより目立つようにする「ビーコン効果(beacon effect)」を狙っている。 |
| 昆虫類(例:コオロギ) | 群れでの鳴き声の同期。 | 同上。 |
| インコ・オウム | 音楽に合わせた動き(例:頭を振る)。 | 音声模倣能力と関連。 |
| ハト | 音の周期性やテンポの識別は可能。 | 拍の知覚は未確認。 |
| カリフォルニアアシカ | 音楽テンポに合わせて動く。 | 音声模倣能力は不明だが、拍の同期能力あり。 |
| マカク | 訓練によりテンポは合わせられるが、拍には遅れて反応。 | 拍の予測的同期は困難。 |
| チンパンジー | 自発的なテンポに近い場合にのみわずかに同期。 | 拍の抽出は未確認。 |
昆虫からヒトまでのこのようなリズム感覚が進化生物学的に共通していた遺伝子によるものなのかはまだ分かっていませんが、ある程度のリズム感覚は継承していそうです。
ヒト固有のリズム感と2拍子の起源は?歩行の誕生が最も重要だった!?
ただし、ヒト(と一部の鳥類)は「Rich BPS (Rich Beat Perception and Synchronization)」という特殊なリズム感覚を発達させていると考えられています(Iversen, 2016)。直訳すると「豊かなビート知覚と同期」です。
Rich BPS は以下の要素で構成されます。
| 構成要素 | 内容 | 他の動物での確認状況 |
|---|---|---|
| 予測的同期 | 音のタイミングを予測して動く(反応ではなく予測)。 | 一部の鳥類で部分的に確認。 |
| 内的拍の生成 | 音がなくても拍を維持できる。 | ヒトのみ明確に確認。 |
| 階層的拍構造の処理 | 複数のテンポ・拍子を同時に処理(例:ポリリズム)。 | オウムで部分的に示唆。 |
| 能動的知覚 | 運動系が聴覚知覚に影響を与える(ASAP仮説)。 | 他種では未確認。 |
| 文化的・訓練による拡張 | 経験や学習によって拍感知能力が向上する。 | ヒトのみ確認済み。 |
要するにリズムを能動的・予測的に理解し続ける力とも言えるかもしれません。これはヒト以外の動物は欠如しているかわずかしかないと今のところ考えられています。
ではRich BPS、そして2拍子の起源はなんであると考えられているのでしょうか?
諸説ありますが、歩行はとても重要な要因であると考えられています(Iversen, 2016; Fitch, 2016)。
二足歩行動物にとってエネルギー的に最も効率的な歩行は等時性(周期が一定である性質)に基づいて行う歩行であると考えられています。そのため、左右の足をテンポよく動かしていきます。
このテンポ感を掴むために全てのヒトは程度の差はあれ本能的にリズム感覚を習得していると考えられています。
「リズムが心地よい」と感じるのは「乳児が歩き始める動機付け」の進化的な副産物であるという考えがありあます。
大人でも散歩をしているとなんとなく心地良いと感じることがありますが、これは言い換えると周期的な前庭覚と聴覚入力を心地よいと感じているということです。
周期的な前庭覚と聴覚入力を通じて歩行を心地よいと感じて歩き始めることの副産物として、聴覚や前庭覚を刺激する運動を伴う歌やダンスを好むことに繋がっていったという説です。
また別の観点として、二足歩行動物が群れで集団で歩くとき、歩行のリズムをあわせることができれば、まさに「足並みが揃っていない」敵集団や捕食者や獲物の足音を聴くことでいち早く察知できる可能性があります。そして集団の規模感も音を重ねることで隠蔽もできます。これも Rich BPS が進化した有力な利点であると言えます。
音楽理論上の2拍子は「強拍・弱拍」でのみ構成されることから単調で、現在では行進曲・マーチ・一部のポピュラーソングに使われる程度で、4拍子にその座を譲っています。
4拍子の起源は?
4拍子は1小節に4拍がある拍子のことで、2拍子と類似していますが、基本的には拍の強さが前から順に「強拍→弱拍→中強拍→弱拍」となっていることから区別されます。ただし拍の強さが4拍子の定義そのものではないので慣例による区分である部分も大きいようです。
4分音符を1拍とした4分の4拍子が現代では最も利用されている拍子で、ロック・ポップス・ダンスミュージック・クラシック・ジャズなど、あらゆるジャンルで幅広く使われています。
では4拍子の元々の起源はなんだと考えられるのでしょうか?
これはやはり歩行であると考えられています(Fitch, 2016)。ただ、この場合歩行の解釈が少し変わります。
歩行しているとき、「右足で蹴る音→右足を上げる音→左足で蹴る音→左足を上げる音」と考えるわけです。
こう考えると「強拍→弱拍→強拍→弱拍」といった拍子が出来上がります。
ただし、「中強拍」の出現について明白な説明をした論文は著者が調べた限りは見当たりません。「中強拍」の存在により複雑さを増して楽しむことができるようになっているのは感覚的には分かりますが科学的には謎なのかもしれません。
近代的な音楽理論に基づいた「強拍→弱拍→中強拍→弱拍」の「4拍子」は17世紀初頭のバロック音楽の舞曲が起源であるとされますが、その成立過程はよく分かっていないようです。
DTMが出現し、あらゆる音楽が再現可能になった現在でも、ポップミュージックとしては以上の2拍子とともに最も広く人類に利用されていることを踏まえると、やはり本能的に歩行に似た偶数拍子を好んでいるのだと考えられます。
ただ、王道ではない変拍子やグルーヴ・レイドバック・プッシュ・オフビート・シンコペーション・スウィングのような複雑な音楽に関してはこの考えだけでは説明できません。王道ではないとはいえ決して無視できず商業的に成立した音楽です。感覚的には「ズレてる方が楽しい・心地良い」と感じる部分も大きいですが、生物学的な由来は大きな謎として残されています。
とはいえ、これらの技法は部分的に挿入されることに価値があるようにも感じます。
3拍子の起源は?
3拍子は1小節に3拍がある拍子のことで、「強拍・弱拍・弱拍」という組み合わせでできており、ワルツやメヌエットなど西洋の舞曲でよく使われる拍子です。
4分音符を1拍とした4分の3拍子や8分音符を2拍とした8分の3拍子が代表的です。
3拍子はどのように生まれたのでしょうか?
もっと古代に生まれている可能性もありますが、ヨーロッパでは中世後期〜ルネサンス初期に登場した計量記譜法(mensural notation)によって、音符の長さが正確に書けるようになります。そこで初めて理論上3拍子が書けるようになりました。
実際に広く3拍子が使われ始めたのは少なくともヨーロッパではワルツが起源であるとされています(Fitch, 2016)。諸説ありますが1580年頃からヨーロッパで流行し始め、ドイツ・オーストリアの民俗舞踊が発展したものだと考えられています(Buurman, 2021)。余談ですが『日本語版Wikipedia』では13世紀に成立したとありますが出典がなく英語版にそのような記載はありません。
ウィンナワルツでは、ターンの間に一連の段階(ステップ→ターン→足を揃える)を挟むことになり、それぞれの「揃える」動作が、反対の足で次のステップを踏み出すための準備の小休憩となります。これにより、右足と左足の両方でステップを踏む合計6段階のサイクルが生成されます。
この回転を伴うという点が独特であり、この行動を伴う場合、3拍子が自然と最適になるとされています。
3拍子はゆったりとしたダンスが生まれてからできた比較的新しい拍子であると言えるでしょう。
他のリズム感覚の進化説は?
リズム感覚の進化には他にもいくつか説がありますので参考のため紹介しておきます(Iversen, 2016; 関・橘,2023)。
音声模倣仮説(Vocal Learning Hypothesis)は音声模倣能力の副産物としてリズム感覚が進化とするものです。オウムとヒトが音声模倣能力と Rich BPS を持っていることが根拠です。ただ非音声模倣動物(アシカなど)でもリズム感覚がある点が矛盾しています。これはあくまで聴覚入力を運動出力に変換する神経回路を獲得するための前適応なのかもしれません。
性選択説(Sexual Selection)は有名な進化心理学者であるジョージ゠ミラーが提唱したもので、音楽能力が配偶者選びに有利だったとするものですが、両性に音楽能力がある点が典型的な性選択と矛盾しています。ただし、男女で音楽の好みの傾向に違いはあるので、リズム感覚が進化した後に、付随的に性選択が起こっている可能性はあります。
社会的絆・集団協調説はリズムが集団の絆形成や協調行動を促進するために進化したとするものです。今の我々がライブ会場で一体感を感じてモッシュピットすることを考えると自然にも思えますが、通常自然選択は個体か濃い血縁集団で起こるもので、このような進化はその通例と異なる「マルチレベル群選択」というものに当たり、進化生物学において解釈に論争があるため、あまりこの考えは好まれません(私は部分的にはあるように思えますが)。それに絆形成の促進ならリズムではなくても良いような気もするので、やはりリズム感覚が進化した後に、付随的に生まれた一体感なのかもしれません。
非適応説(音楽は副産物)はこれも有名な心理学者であるスティーブン゠ピンカーが提唱したもので、音楽は「聴覚的チーズケーキ」、つまり快楽技術であり、進化的適応ではないという説です。確かに現代の心地よい音楽はチーズケーキのようなものかもしれませんが、そもそものリズム感覚は流石に進化的な産物ではありそうです。
現状は根本的なリズム感覚は歩行に伴う進化という考えが有力であるように私には思えますが、今後の研究次第で変わってくるかもしれません。
引用文献
Buurman, E. 2021. Early Viennese Waltz Dances. In: The Viennese Ballroom in the Age of Beethoven. pp.32-54. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN: 9781108797856, https://doi.org/10.1017/9781108863278.003
Fitch, W. T. 2016. Dance, music, meter and groove: a forgotten partnership. Frontiers in Human Neuroscience 10: 64. https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00064
Iversen, J. R. 2016. 21 In the beginning was the beat: evolutionary origins of musical rhythm in humans. In: The Cambridge Companion to Percussion. pp.281-295. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN: 9781107472433, https://doi.org/10.1017/CBO9781316145074.022
関義正・橘亮輔. 2023. 動物のリズム同調能力とその源泉. 日本音響学会誌 80(1): 33-40. https://doi.org/10.20697/jasj.80.1_33