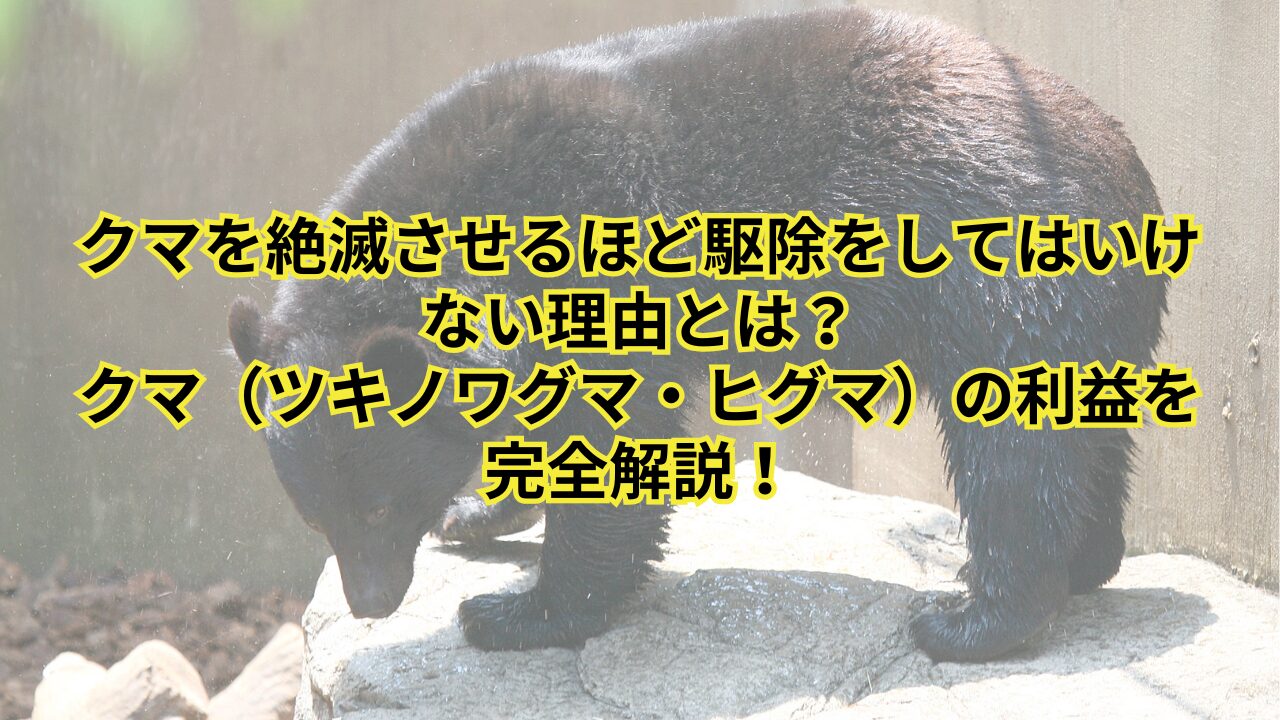日本には本州と四国にニホンツキノワグマ(日本月輪熊) Ursus thibetanus japonicus が、北海道にエゾヒグマ (蝦夷羆)Ursus arctos yesoensis が分布しています。
2025年これらのクマが人里での活動を増加させ、痛ましい事件が頻発していることが報道されています。このようなクマによる被害は古代からありますし、日本だけでなく世界中で問題になるテーマです。
その中で「クマはどのように我々の生活と関わっているの?」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか?
中には「クマを絶滅させるべき!」という極端な意見を持つ人も居ます。そのような意見を持つのは自由だと思いますが、クマが生態系を介して与えてくれている恩恵についての知識が不足している部分もあるのではないかと思います。
私は必要に応じてクマの駆除はやむを得ないと考えていますが、ここでは環境アセスメント業務従事者としてあえて動物愛護の観点ではなく、どのような実利的な恩恵(ヒトにとっての利点・メリット)があるのかについて考えてみます。
端的にまとめると「クマは種子散布や捕食を通じて森林を豊かにし、その森林が人に与える恩恵によって間接的に恩恵を与えている」と言えるでしょう。
理由1:種子散布が減り森林が減ったり単純な森林が増えてしまうから
ニホンツキノワグマは雑食ではありますがその80~90%が植物性の餌を食べていることが分かっています(橋本・高槻,1997)。
その中でも23種類の植物の果実を食べ、糞の調査から16種類の植物の種子を生きたまま外に出していることも分かっています(小池ら,2003)。
その植物にはヤマザクラなど6種類のサクラが含まれており、花見好きの日本人にとって身近で馴染み深い植物も含まれています。
加えて単に種数だけでなく、例えばヤマザクラではニホンツキノワグマによって地理的に高標高に分布が押し上げられているという研究もあります(Naoe et al., 2016)。
ヒグマでも同様で、アメリカ合衆国アラスカ南東部と北部では主要なベリー類の低木であるアメリカハリブキ Oplopanax horridus の種子の大部分を鳥ではなくクマが散布していることを報告されています(Levi et al., 2020)。
エゾヒグマではまだ研究が不足していますが、やはりベリー類を食べることから同様の役割を持っていると考えられており(佐藤,2005;2018)、ある研究ではサルナシなど3種類のベリーを食べた後、ほとんどの種子はそのまま排泄され、破損していないものが94%な上に、発芽率を高めていました(Tsunamoto et al., 2024)。
それだけではなくヒグマでは種子食のげっ歯類に糞を通じて餌を供給していることも確認されています(Levi et al., 2020)。うんちの中の種子をネズミが好んで運んでいきます。
つまりこれはクマが森林の植物や動物の多様性を増加させているということです。
森林は大気の二酸化炭素を固定してバイオマスにしたり、「緑のダム」として雨水を吸収することで洪水や水不足のリスクを低下させたり、地盤を安定させがけ崩れや土石流を防いだり、気候を調整したり、レクリエーションの場を提供するなど様々な「生態系サービス」を与えてくれることはよく知られています(中静,2017;田中・長廣,2019)。
更に森林で育った昆虫達が私達の農産物の受粉に貢献していることも多くの研究で分かっており(Ulyshen et al., 2023)、多くの農作物は野生の昆虫の受粉なしには果実をつけることができません。例えば日本でもソバの受粉が森林由来の昆虫によって促されていることが分かっています(Taki et al., 2010)。
これらの生態系サービスは森林の生物多様性が高いほど多いこともよく分かっています(Brockerhoff et al., 2017)。
したがって、クマが存在することは間接的に人間にとっても利益になっている可能性は高いです。
ただそれが全体に対してどの程度のものなのかは現在では未知であると言えるでしょう。
理由2:ハチを駆除してくれるから
ニホンツキノワグマはミツバチやスズメバチやアリの仲間も好んで食べています(橋本・高槻,1997)。動物質の餌の中では最も割合が多いです。これは真社会性昆虫なのでコロニーとして存在しているからで、ニホンツキノワグマにとって重要なタンパク質源となっています。エゾヒグマについても同様です(佐藤,2005)。
特に人間にとってミツバチやスズメバチは攻撃性が昆虫の中では比較的高く毒針を持っているので被害が多く、スズメバチでは2002~2011年の10年間では平均で19.4人の死亡者が出ています(金山,2013)。負傷はもっと多いでしょう。
このようなミツバチやスズメバチをニホンツキノワグマは捕食によって個体数を減らしている可能性があります。特にスズメバチは昆虫の中ではほぼ最上位捕食者なため数えるほどしか天敵がいないことに加え(Noguchi & Ikeda, 2022)、脊椎動物だとしても鳥のハチクマや哺乳類のテンなど証明されている天敵は限られています(Hirakawa & Sayama, 2005)。
ニホンツキノワグマはミツバチやスズメバチにとって重要な天敵の1つであることは間違いなく、人間にとっても恩恵をもたらしている可能性が高いです。ただし量的な部分は未解明です。
ヒトにとっての利点という観点では「クマとスズメバチの駆除どちらが大事?」という話にもなってしまいますが、私はスズメバチに遭遇した回数の方が圧倒的に多くはあります。
更にスズメバチは昆虫の中では最上位捕食者であることから様々な昆虫を捕食しています。外来種としてハワイとニュージーランドに侵入したスズメバチは蛾や蝶の幼虫を中心に在来の生態系に大きな影響を与えていることが知られています(New, 2016)。
日本ではニホンツキノワグマがスズメバチの個体数を減らし捕食圧が低下することで被食者や下位捕食者の多様性を上昇させているかもしれません。これは上述の生態系サービスの上昇に繋がるでしょう。
理由3:サケの捕食を通じて海の栄養を地上にばらまくから
ニホンツキノワグマでは魚類を食べている例は今のところ確認されていませんが(橋本・高槻,1997)、エゾヒグマでは量は開発で減少傾向にあるもののカラフトマスやシロザケなどのサケ科魚類を食べていることが確認されています(佐藤,2005)。その捕食圧はカラフトマスの繁殖時の形態を変化させてしまうほどで(佐橋ら,2020)、冬眠前の重要な餌資源となっており、メスはサケ類の利用量が増えるほど多く子供が産めるという研究もあります(佐藤,2018)。
これだけ聴くとただの捕食にも聞こえますが、実はこれほど多くサケ類を食べることによってエゾヒグマは窒素を中心に海の栄養塩を地上に戻しているのです(Koshino et al., 2013; 佐藤,2018)。これは盲点かもしれませんね。
これは日本のエゾヒグマだけでなく世界中のヒグマで同様であることが指摘されています(Levi et al., , 2020)。
しかも、糞を介して森を豊かにするだけでなく、殺したサケの死骸を陸生動物や水生昆虫が利用するため、河川内も豊かにしていることも分かっています。
普通に考えれば栄養塩は重力に従って川から流れていってしまうわけですが、そうならないのはサケとヒグマのおかげであると言えるでしょう。
ただ、「窒素なら海鳥の糞で内陸に運ばれたり、マメ科などの植物が窒素固定を介して、空気中の窒素を土壌に還元しているから問題ないのでは?」という疑問も浮かぶかもしれません。
ところが、窒素の同位体比の調査によって河岸植物では活発にサケ由来の窒素を利用し、生理活動・生産性・群集構造を増加させ、体内の窒素比が増えたり、気孔の密度を上昇させるなど具体的な変化もあることがいくつもの研究で確認されています(Levi et al., 2020)。
同様のことができるのはほぼクマに限られ、サケ類を食べる動物でも食べるのはクマの捕食活動後や洪水後の死骸です。
従ってエゾヒグマは北海道の河川や河川沿いの森林を豊かにする大きな役割を持っている可能性があります。
理由4:掘り返し行動で土地を豊かにするから
ヒグマでは雪田群落など亜高山性草原で草本類の地下部を掘り返すことが知られています(佐藤,2018)。これは日本のエゾヒグマでも同様です。
国内での研究は不足していますが、アメリカ合衆国モンタナ州グレイシャー国立公園ではこの「掘り返し」行動によって裸地が増え、土壌中のアンモニアや硝酸塩濃度が上昇し、キバナカタクリという植物の種子の生産量も上昇したことが報告されています。
つまりヒグマの摂食行動がやはり土壌の豊かさの上昇に繋がっているのです。このようにある行動によって地形を改変し、他の生物の生息地を生み出す生物を「生態系エンジニア」と呼び、ミミズやビーバーがその代表ですが、ヒグマもその一員であることが示されています。
理由5:草食動物を食べて土に還しているから
ニホンツキノワグマではニホンカモシカとニホンジカを、エゾヒグマではエゾジカを食べることが知られています(橋本・高槻,1997;佐藤,2005)。
ただし、直接生きているものを食べる事例は弱っている個体を除いて少なく、基本的には狩猟や駆除で殺された死体を食べていると考えられています(橋本・高槻,1997;佐藤,2018)。
海外のヒグマでは草食動物の幼獣を襲うことがあるので、ニホンツキノワグマやエゾヒグマを直接観察できる例が少ないことも踏まえるともっと捕食している可能性もありますが、今のところ分かっていません。
もし捕食している場合は草食哺乳類の個体数を調整しているかもしれません。
また腐肉食であった場合でも、草食哺乳類を土に還す役割を担っていると言えます。
ただこの役割は別の多くの動物で代替可能かもしれません。
理由6:キノコを食べて胞子を散布するから
北米に分布するアメリカグマ Ursus americanus やハイイログマUrsus arctos horribilis ではキノコ(子嚢菌・担子菌に含まれる菌根菌)を食べて、一部の胞子を生きたまま消化管を通過させ排泄していることが分かっています(Cázares & Trappe, 1994; Mattson et al., 2002)。
これによって移動力の低い菌類をより広い地域に分布させ、菌類の多様性、そして寄生先の植物の多様性の増加に貢献している可能性があります。更に菌根菌の子実体に生息する自由生活性の窒素固定細菌も、哺乳類の菌食によって菌の胞子とともに拡散します。
勿論、きのこ狩りが趣味な人は直接恩恵を受けています。
日本ではここまで調べられていませんが、ニホンツキノワグマもキノコを食べることは知られているので(橋本・高槻,1997)、同様の役割があると考えられます。ただし、リス・モモンガ・ネズミ・ニホンザルなどもキノコは食べています(澤田,2014;相良,2021)。
最後に:クマの役割は代替可能か?
ここまで様々な生態系を通じたクマのメリットを挙げてきましたが、実際の生態系全体に対しての影響力は研究が不足しており未知です。
九州のツキノワグマは昭和初期にはすでに生息域も限られ生息数は僅かで、1957年の発見を最後に絶滅していますが(西田ら,2022)、それによって上述のような影響が出ているのかは分かっていません。
とはいえ、人間の想像力には限界があり、不可逆な絶滅によって出る影響を全て考慮するのは不可能に近いでしょう。
「リベット仮説」として知られるように、飛行機の部品のように1つが抜け落ちても飛ぶことができても(1種が消えても生態系は変わらないように見えても)、その数が増えていくにつれて急激に飛ぶことができなくなっていく(生態系が崩壊する)ということもありえます(Eisenhauer et al., 2023)。近年では「冗長性」という用語に変わってそのことが実証されつつあります。
クマでも現状は他の動物によってその役割が代替される可能性もありますが、他の生物の絶滅が重なってくると本当にそうなるかは分かりません。
漫画『ゴールデンカムイ』でも出てきましたが、かつてアイヌが人を襲わない良いヒグマであるキムンカムイと人を襲う悪いヒグマであるウェンカムイを区別して対処を分けたように、和人もこのような考えを取り入れて対処すべきという考えもあります(松田,2008)。絶滅させることがコスト的にも利害的にも倫理的にも非合理であることを考えると、私もこれを1つの例として自然の両面性を考え、理性的な共生が求められていると考えています。
勿論、駆除と保護のバランスはとても難しいものなので上述のような影響を参考に議論を深めてください。
引用文献
Brockerhoff, E. G., Barbaro, L., Castagneyrol, B., Forrester, D. I., Gardiner, B., González-Olabarria, J. R., … & Jactel, H. 2017. Forest biodiversity, ecosystem functioning and the provision of ecosystem services. Biodiversity and Conservation 26(13): 3005-3035. https://doi.org/10.1007/s10531-017-1453-2
Cázares, E., & Trappe, J. M. 1994. Spore dispersal of ectomycorrhizal fungi on a glacier forefront by mammal mycophagy. Mycologia 86(4): 507-510. https://doi.org/10.1080/00275514.1994.12026443
Eisenhauer, N., Hines, J., Maestre, F. T., & Rillig, M. C. 2023. Reconsidering functional redundancy in biodiversity research. npj Biodiversity 2(1): 9. https://doi.org/10.1038/s44185-023-00015-5
金山彰宏. 2013. ハチの種類と防除法. Pest Control Tokyo (64): 20-25. https://www.pestcontrol-tokyo.jp/img/pub/064r/064-8.pdf
小池伸介・羽澄俊裕・古林賢恒. 2003. ニホンツキノワグマ (Ursus thibetanus japonicus) の種子散布者の可能性. 野生生物保護 8(1): 19-30. https://doi.org/10.20798/wildlifeconsjp.8.1_19
Koshino, Y., Kudo, H., & Kaeriyama, M. 2013. Stable isotope evidence indicates the incorporation into Japanese catchments of marine-derived nutrients transported by spawning Pacific Salmon. Freshwater Biology 58(9): 1864-1877. https://doi.org/10.1111/fwb.12175
Levi, T., Hilderbrand, G. V., Hocking, M. D., Quinn, T. P., White, K. S., Adams, M. S., … & Wilmers, C. C. 2020. Community ecology and conservation of bear-salmon ecosystems. Frontiers in Ecology and Evolution 8: 513304. https://doi.org/10.3389/fevo.2020.513304
Mattson, D. J., Podruzny, S. R., & Haroldson, M. A. 2002. Consumption of fungal sporocarps by Yellowstone grizzly bears. Ursus 13: 95-103. https://www.jstor.org/stable/3873191
松田裕之. 2008. やりなおしサイエンス講座07 なぜ生態系を守るのか?. NTT出版, 東京. 240pp. ISBN: 9784757160279
中静透. 2017. 陸域の生物多様性と生態系サービス. 農村計画学会誌 36(1): 5-8. https://doi.org/10.2750/arp.36.5
橋本幸彦・高槻成紀. 1997. ツキノワグマの食性: 総説. 哺乳類科学 37(1): 1-19. https://doi.org/10.11238/mammalianscience.37.1
Hirakawa, H., & Sayama, K. 2005. Photographic evidence of predation by martens (Martes melampus) on vespine wasp nests. Bulletin of the Forestry and Forest Products Research Institute 4(3): 207-210. ISSN: 0916-4405, https://www.ffpri.go.jp/labs/kanko/396-3.pdf
佐橋玄記・森田健太郎・芳山拓. 2020. 同じ種。でも結構違う?~サケ科魚類の野生魚にみられる種内の多様性~. salmon 情報 14: 3-9. https://fra.repo.nii.ac.jp/records/2009605
Naoe, S., Tayasu, I., Sakai, Y., Masaki, T., Kobayashi, K., Nakajima, A., … & Koike, S. 2016. Mountain-climbing bears protect cherry species from global warming through vertical seed dispersal. Current Biology 26(8): R315-R316. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.002
New, T. R. 2016. Alien insects and insect conservation. In Alien species and insect conservation. pp. 129-174. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-38774-1_6
西田伸・川原一之・安河内彦輝・江田真毅・小池裕子・岩本俊孝. 2022. 宮崎県高千穂町における 「熊の手」 の由来とその分子系統解析―九州・祖母山系産ツキノワグマのDNA解析―. 哺乳類科学 62(1): 3-10. https://doi.org/10.11238/mammalianscience.62.3
Noguchi, D., & Ikeda, K. 2022. Intraguild predation on hornets and yellowjackets of vespine wasps by spiders, and vice versa. Serket 18(3): 287-298. http://hdl.handle.net/10069/00041479
相良直彦. 2021. きのこと動物. 築地書館, 東京. 274pp. ISBN: 9784806716150
佐藤喜和. 2005. ヒグマの食性―地域による違いと年変動―. 哺乳類科学 45(1): 79-84. https://doi.org/10.11238/mammalianscience.45.79
佐藤喜和. 2018. ヒグマの生息地としての森林とその管理―天然林・人工林・林床植生そしてシカ. 北方森林研究 66: 1-3. https://doi.org/10.24494/jfsh.66.0_1
澤田晶子. 2014. 霊長類のキノコ食行動―今後の課題と可能性. 霊長類研究 30(1): 5-21. https://doi.org/10.2354/psj.30.010
Taki, H., Okabe, K., Yamaura, Y., Matsuura, T., Sueyoshi, M., Makino, S. I., & Maeto, K. 2010. Effects of landscape metrics on Apis and non-Apis pollinators and seed set in common buckwheat. Basic and Applied Ecology 11(7): 594-602. ISSN: 1439-1791, https://doi.org/10.1016/j.baae.2010.08.004
田中勝也・長廣修平. 2019. 森林の生態系サービスの価値に対する主観評価と推論評価の比較. 環境経済・政策研究 12(1): 44-58. https://doi.org/10.14927/reeps.12.1_44
Tsunamoto, Y., Tsuruga, H., Kobayashi, K., Sukegawa, T., & Asakura, T. 2024. Seed dispersal function of the brown bear Ursus arctos on Hokkaido Island in northern Japan: gut passage time, dispersal distance, germination, and effects of remaining pulp. Oecologia 204(3): 505-515. https://doi.org/10.1007/s00442-024-05510-5
Ulyshen, M., Urban-Mead, K. R., Dorey, J. B., & Rivers, J. W. 2023. Forests are critically important to global pollinator diversity and enhance pollination in adjacent crops. Biological Reviews 98(4): 1118-1141. https://doi.org/10.1111/brv.12947