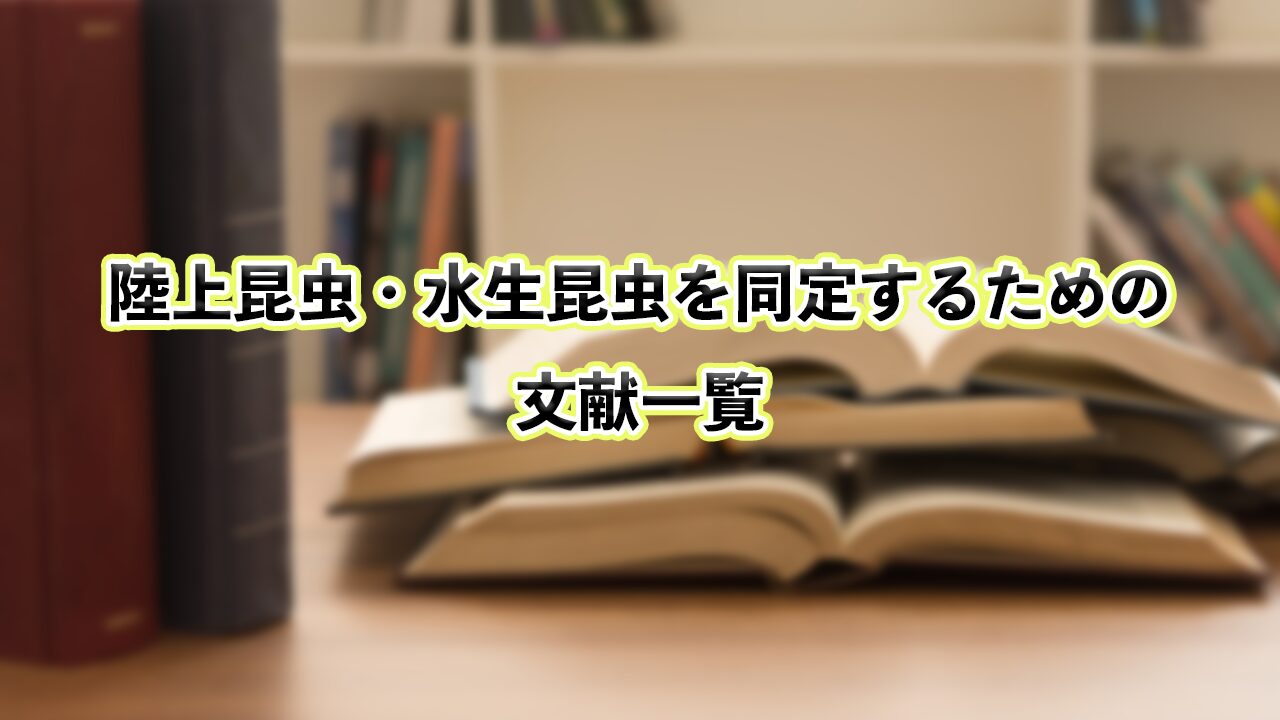本記事では昆虫を同定するための文献を収集していきます。基本的に検索表が載っており種まで確実に同定できるものを中心に集めています。全ての分類群を対象としてますが、あくまで個人的に必要・目撃した文献を収集しているため、完全網羅するものではありません。最新の文献がありましたらぜひメールよりご紹介ください。
昆虫全般の同定文献
『原色日本昆虫図鑑 下 全改訂新版』
伊藤修四郎・奥谷禎一・日浦勇. 1977. 原色日本昆虫図鑑 下 全改訂新版. 保育社, 大阪. 385pp. ISBN: 9784586300037
『原色昆虫大圖鑑 第3巻 トンボ目・カワゲラ目・バッタ目・カメムシ目・ハエ目・ハチ目他 新訂』
平嶋義宏・森本桂. 2008. 原色昆虫大圖鑑 第3巻 トンボ目・カワゲラ目・バッタ目・カメムシ目・ハエ目・ハチ目他 新訂. 北隆館, 東京. 654pp. ISBN: 9784832608276
昭和34年初版発行の『原色昆虫大圖鑑』(全3巻)を全面改訂。第III巻は I・II巻に掲載したチョウ・コウチュウ両目以外の30目約3,200種を掲載。和名・学名・分布などの記載を今日の分類基準にあわせ全面的に見直した他、RDB対象種などを中心に追加種を掲載。
『北隆館ホームページ』
『絵解きで調べる昆虫1 環境アセスメント動物調査講演会 絵解き検索シリーズ総編集』
初宿成彦. 2013. 絵解きで調べる昆虫1 環境アセスメント動物調査講演会 絵解き検索シリーズ総編集. 文教出版, 大阪. 243pp. http://kandoukon.org/sub/etoki.html
本書は環境アセスメント動物調査手法の昆虫分野の総集編。絵解きでとても分かりやすい検索図鑑となっています。
『日本環境動物昆虫学会ホームページ』
【目次】
- 同翅類とヨコバイ科の絵解き検索
- ハチ目昆虫の検索と解説
- ハバチ・キバチ類(ハチ目広腰亜目)の絵解き検索
- 絵解き検索による分類の解説 双翅目昆虫の見分け方
- 日本産ミギワバエ科の属の絵解き検索
- ピットフォールトラップによる地表性甲虫の調査
- オサムシ科甲虫の絵解き検索による見分け方
- ジョウカイボン科甲虫の絵解き検索
- コメツキムシの絵解き検索
- 日本産ハナノミダマシの絵解き検索
- 絵解き検索によるゾウムシ類の見分け方
- 絵解き検索による小蛾類の見分け方
『絵解きで調べる昆虫2 環境アセスメント動物調査講演会 絵解き検索シリーズ総編集』
初宿成彦. 2017. 絵解きで調べる昆虫2 環境アセスメント動物調査講演会 絵解き検索シリーズ総編集. 文教出版, 大阪. 243pp. ISBN: 9784938489251
環境アセスメント動物調査手法の昆虫分野の総集編、第2弾です。
『六本脚ホームページ』
絵解きでとても分かりやすい検索図鑑となっています。
前巻と合わせて、合計17の分類群について解説されています。
【目次】
- キジラミ類(カメムシ目)の絵解き検索(改訂版) 5
- カスミカメムシ類の絵解き検索 53
- 日本産ヒロバカゲロウ科(アミメカゲロウ目)の絵解き検索 91
- ベニボタル科の絵解き検索 103
- ユスリカ科の絵解き検索―エリユスリカ亜科・ユスリカ亜科― 129
『新版 屋内でみられる小蛾類 食品に混入するガのプロフィール』
那須義次・広渡俊哉. 2019. 新版 屋内でみられる小蛾類 食品に混入するガのプロフィール. 文教出版, 大阪. 174pp. http://kandoukon.org/sub/ga.html
本書のもとになったのは、2004年に出版された初版の『屋内でみられる小蛾類—食品に混入するガのプロフィール』です。当時は品質管理の重要性が認識されてきたせいか、私たちガ類の専門家に食品等に混入する種の同定依頼が増えていました。送られてくる検体は、たいてい鱗粉がとれたものですから、図鑑で斑紋を比べて同定するのは困難です。そのような場合、交尾器の形態を調べることによって同定が可能になることが多いのですが、いくら交尾器を観察できても、日本には屋内でみられるガ類の交尾器をまとめて図示した参考書がないことに気づきました。そうした中、高木良吉氏(環境管理技術研究会・文教出版)に依頼されて、2000~2002年に、雑誌『環境管理技術』に食品に混入する種を中心とした「屋内でみられる小蛾類」についての連載を広渡が担当することになりました。内容は、屋内でみられる小蛾類について毎号1種ずつの成虫の全体図と交尾器を図示し、その昆虫に関連した話題を提供するというものでした。初版では、合計16回にわたったこの連載をとりまとめ、16種を紹介しました。
『日本環境動物昆虫学会ホームページ』
ところで、食品に混入するガ類、すなわち食品や衣類を直接食べて加害するのは成虫ではなく幼虫です。しかし、幼虫はお互いによく似ており、形態の違いなどは一般的にあまり知られていません。そこで、那須が2015~2017年に、「屋内でみられる小蛾類の幼生期」と題して、同じく『環境管理技術』に毎号1種ずつの幼虫と蛹について連載することになりました。そして、この16回にわたる連載が終了した後に、成虫と幼生期の情報を合体した『新版 屋内でみられる小蛾類—食品に混入するガのプロフィール』の出版を企画するに至りました。新版では、合計28種以上の屋内でみられる小蛾類を紹介し、同定の助けとなるように成虫、幼虫および蛹の絵解き検索を追加しました。交尾器を含む成虫の形態だけでなく、幼虫や蛹の形態や識別点についてもできるだけ解説しました。
【目次】
- はじめに
- 屋内で発生する小蛾類
- 形態の特徴と観察
- 各種の解説
- 絵解き検索(成虫の検索表・幼虫の検索表・蛹の検索表)
- 参考文献
水生昆虫の同定文献
『日本産水生昆虫 科・属・種への検索 第二版』
川合禎次・谷田一三. 2018. 日本産水生昆虫 科・属・種への検索 第二版. 東海大学出版部, 平塚. 1752pp. ISBN: 9784486017745
2005年刊行の全面改定版。引きやすい検索表と体長・分布域など種の特徴記載を充実させ、一部の種では写真による検索も可能。2005年刊行の全面改定版。
『紀伊國屋書店ウェブストア』
最新の分類法に基づき、引きやすい検索表と、体長・分布域など種の特徴記載を充実させ、一部の種では写真による検索も可能になった。
最新の水生昆虫の知見が得られる、昆虫研究者に必携の書。
【目次】
- 総説
- 水生昆虫とは
- 水への適応
- 水生昆虫研究の史的展望
- 各論
- カゲロウ目
- トンボ目
- カワゲラ目
- 半翅目
- ヘビトンボ目
- アミメカゲロウ目
- トビケラ目
- ハチ目
- チョウガ目
- 甲虫目
- 双翅目
- ニセヒメガガンボ科
- ガガンボ科
- アミカ科
- アミカモドキ科
- ハネカ科
- チョウバエ科
- コシボソガガンボ科
- ホソガ科
- カ科
- ブユ科
- ヌカカ科
- ユスリカ科
- アブ科
- ナガレアブ科
- ミズアブ科
- アシナガバエ科
- ヤチバエ科
- ミヤギバエ科
- ニセミギワバエ科
- フンバエ科
- イエバエ科
- ハナバエ科
- ベッコウバエ科
『原色川虫図鑑 成虫編 カゲロウ・カワゲラ・トビケラ』
丸山博紀・花田聡子. 2016. 原色川虫図鑑 成虫編 カゲロウ・カワゲラ・トビケラ. 全国農村教育協会, 東京. 482pp. ISBN: 9784881371848
『幼虫編』と合わせて川虫の一生がわかる!
『全国農村教育協会ホームページ』
- 川虫の成虫は、幼虫に比べると比較的見分けが容易です。
- カゲロウ目13科40属84種、カワゲラ目9科56属102種、トビケラ目28科102属163種、計50科198属349種を豊富な写真と図版で掲載しました。カゲロウ目については亜成虫も掲載しました。
- 科・属の検索表の併用で種の特徴、見分け方、生息場所、発生時期を詳しく解説し、種の同定に役立ちます。
- カゲロウ目・カワゲラ目・トビケラ目の日本産種のリストを掲載し、成虫編・幼虫編の各解説番号を付して成虫と幼虫の情報を統合しました。
トンボ目の同定文献
『日本産水生昆虫 科・属・種への検索 第二版』があれば成虫、幼虫ともに同定可能ですが、『日本産トンボ幼虫・成虫検索図説』では絵解き検索が可能です。
『日本産トンボ幼虫・成虫検索図説』
1987年現在、わが国には14科83属181種14亜種のトンボが生息している。江戸時代の末期、尾張の本草学者であった吉田雀巣庵が『蜻蛉譜』を著し、65匹のトンボを図説したのがわが国におけるトンボ類図鑑の最初である。その後、トンボを図示解説した図鑑はこれまでにいろいろ発刊されているが、本図説では、生きている姿そのままの生態写真で収録することにした。雌雄で体形や色彩・斑紋の違うもの、成熟するにつれて色彩が極端に変化する種、2通り以上の異なった色彩・斑紋が現われる多型のみられる種についてもできるだけ網羅するように努めた。幼虫も代表的な種の生態写真を載せることにした。
『紀伊國屋書店ウェブストア』
【目次】
- 日本列島のトンボ相
- カラー生態写真
- 成虫検索図
- 幼虫検索図
- 均翅亜目
- ムカシトンボ亜目
- 不均翅亜目
ガロアムシ目・ハサミムシ目・ナナフシ目・カマキリ目・ゴキブリ目・シロアリ目・バッタ目の同定文献
『日本産直翅類標準図鑑』
日本直翅類学会. 2016. 日本産直翅類標準図鑑. 学研プラス, 東京. 384pp. ISBN: 9784054064478
日本産に産する直翅類昆虫(多新翅類)をバッタのみならず、これまでなかったガロアムシ目、ハサミムシ目、ナナフシ目、シロアリモドキ目、カマキリ目、ゴキブリ目、シロアリ目まであつかった図鑑。日本産をほぼ網羅し、解説には検索表がついている。
『学研出版サイト』
【目次】
- 用語解説 6
- この図鑑の使い方 8
- 図版
- ガロアムシ目 10
- ハサミムシ目 12
- ナナフシ目 20
- シロアリモドキ目 43
- カマキリ目 44
- ゴキブリ目 68
- シロアリ目 79
- バッタ目 84
- 解説
- 多新翅類の系統(町田龍一郎) 164
- ガロアムシ目(中浜直之,内舩俊樹) 167
- ガロアムシ科 168
- ハサミムシ目(西川勝) 170
- ドウボソハサミムシ科 171
- ムナボソハサミムシ科 172
- ハサミムシ科 173
- オオハサミムシ科 177
- カザリハサミムシ科 178
- テブクロハサミムシ科 181
- クギヌキハサミムシ科 182
- ナナフシ目(市川顕彦) 187
- コブナナフシ科 187
- ナナフシモドキ科 189
- トビナナフシ科 191
- シロアリモドキ目(市川顕彦) 196
- シロアリモドキ科 196
- カマキリ目(中峰空) 198
- ハナカマキリ科 198
- カマキリ科 199
- ゴキブリ目(旭和也,遠藤拓也,小松謙之) 206
- ゴキブリ科 207
- チャバネゴキブリ科 211
- オオゴキブリ科 219
- ムカシゴキブリ科 225
- ホラアナゴキブリ科 226
- シロアリ目(冨永修) 228
- オオシロアリ科 228
- レイビシロアリ科 233
- ミゾガシラシロアリ科 235
- シロアリ科 239
- バッタ目(加納康嗣,河合正人,市川顕彦,冨永修,村井貴史) 242
- コオロギ科 244
- マツムシ科 253
- ヒバリモドキ科 258
- カネタタキ科 268
- アリツカコオロギ科 270
- ケラ科 271
- カマドウマ科 272
- クロギリス科 287
- コロギス科 287
- キリギリス科 290
- ササキリモドキ科 308
- ヒルギササキリモドキ科 321
- クツワムシ科 321
- ヒラタツユムシ科 322
- ツユムシ科 322
- ノミバッタ科 332
- ヒシバッタ科 335
- クビナガバッタ科 344
- オンブバッタ科 345
- バッタ科 346
- 引用文献 372
- 索引 378
- 和名索引
カメムシ目の同定文献
『日本原色カメムシ図鑑 陸生カメムシ類 第1巻』
安永智秀・高井幹夫・山下泉・川村満・川澤哲夫. 1993. 日本原色カメムシ図鑑 陸生カメムシ類 第1巻,全国農村教育協会,東京.380pp. ISBN: 9784881370520
カメムシ類には大きくわけて3つの側面があります。
- ひとつは、キンカメムシ科など美しい色彩を持っているカメムシ。
- ひとつは、斑点米の原因となるアカヒゲホソミドリカスミカメなど農作物の重要な害虫としてのカメムシ。
- そして、害虫の天敵としてのカメムシ。
前者は、昆虫愛好家の方たちの興味の対象になり、後の2つは農業者や農業関係の研究・指導者の方々にとって、重大な関心のある対象となっています。
『全国農村教育協会ホームページ』
本書は、これら多様な側面を持つカメムシについて、カラー生態写真をふんだんに使って解説したもので、昆虫愛好家から農業関係者・昆虫専門家まで、幅広くお使いいただける利用価値の高い原色図鑑です。
『日本原色カメムシ図鑑 陸生カメムシ類 第2巻』
安永智秀・高井幹夫・中谷至伸. 2001. 日本原色カメムシ図鑑 陸生カメムシ類 第2巻. 全国農村教育協会, 東京. 350pp. ISBN: 9784881370896
1993年発刊の『日本原色カメムシ図鑑』は、23科353種の日本産陸生カメムシを掲載したわが国初の総合的カメムシ図鑑として高評を博してきました。それから8年、研究者らの精力的な活動によって、カメムシの分類は長足の進歩をとげ、多くの新種が発見されると同時に分類の体系も見直されています。
とりわけカスミカメムシ科(旧メクラカメムシ科)はカメムシ目昆虫の中で最大のグループでありながら、8年前には81種が掲載されるにとどまっていました。本書では404種のカスミカメムシが明らかにされ、その食性についても、従来は草食性だと考えられていたものが、むしろ雑食性が基本で、中にはもっぱら肉食性が中心のものもいることが明らかにされました。これは、天敵としての大きな可能性を示唆しています。このような先端情報を満載してお届けするのが本書『日本原色カメムシ図鑑第2巻』です。【掲載種】
『全国農村教育協会ホームページ』
カスミカメムシ科 404種
ハナカメムシ科 40種
フタガタカメムシ科 1種
トコジラミ科 2種
【目次】
- カメムシ類の分類体系
- 日本産の分類群の解説
- 各論
- フタガタカメムシ科 Microphysidae
- カスミカメムシ(メクラカメムシ)科 Miridae
- ハナカメムシ科 Anthocoridae
- トコジラミ科 Cimicidae
- 応用上重要なカスミカメムシ類
- 雄交尾器の解剖と観察法
- 文献
- 主な用語集
『日本原色カメムシ図鑑 陸生カメムシ類 第3巻』
石川忠・高井幹夫・安永智秀. 2012. 日本原色カメムシ図鑑 陸生カメムシ類 第3巻. 全国農村教育協会, 東京.ISBN: 9784881371688
1993年発刊の『日本原色カメムシ図鑑(第1巻)』は、発刊当時知られていた日本産陸生カメムシの約半数に当たる358種を掲載し、カメムシ全体を総合的に概観した原色図鑑です。
『全国農村教育協会ホームページ』
続く『日本原色カメムシ図鑑 第2巻』は2001年に発刊され、難分類群の代表格であるカスミカメムシ類とハナカメムシ類を中心に4科447種を詳述しました。
第3巻となる本書では、第2巻で取り上げられなかった29科665種を詳述します。第1巻発刊後およそ20年間の研究成果がいかんなく発揮され、新種はもちろん、第1巻既出種についてもその大多数を改訂のうえ詳述しています。グンバイムシ科、サシガメ科、ヒラタカメムシ科、ナガカメムシ上科をはじめ極めて多様性に富むグループが鮮明な生態写真を伴って登場します。また細密図を使った形態解説に加え、全科への検索を可能にする「絵解き検索」でさらに進化し、使いやすくなりました。
【目次】
- カメムシの分類体系
- カメムシ類の分類体系
- ナガカメムシ上科の分類体系
- カメムシの形態
- カメムシ類の形態
- 陸生カメムシ類の科への絵解き検索
- 日本産の分類群の解説/カラー図版と解説
- クビナガカメムシ科
- グンバイムシ科
- マキバサシガメ科
- サシガメ科
- ヒラタカメムシ科
- クロマダラナガカメムシ科
- ヒゲナガカメムシ科
- ヒョウタンナガカメムシ科
- オオメナガカメムシ科
- コバネナガカメムシ科
- マダラナガカメムシ科
- チビカメムシ科
- ヒメヒラタナガカメムシ科
- ホソメダカナガカメムシ科
- メダカナガカメムシ科
- イトカメムシ科
- オオホシカメムシ科
- ホシカメムシ科
- ツノヘリカメムシ科
- ホソヘリカメムシ科
- ヒメヘリカメムシ科
- ヘリカメムシ科
- クヌギカメムシ科
- マルカメムシ科
- ツチカメムシ科
- キンカメムシ科
- ノコギリカメムシ科
- カメムシ科
- ツノカメムシ科
- 随想 45本
- カメムシ学名索引(第1巻の掲載ページも記載)
- カメムシ和名索引(第1巻の掲載ページも記載)
- 植物和名索引
その他論文
Matsumura, S. 1935. Revision of Stenocranus Fieb.(Hom.) and its allied species in Japan-Empire. Insecta matsumurana 9(4): 125-140. http://hdl.handle.net/2115/9297
ハチ目の同定文献
『神奈川県立生命の星・地球博物館 特別出版物 第2号 日本産ヒメバチ上科(膜翅目)の属への検索表』
渡辺恭平・藤江隼平. 2022. 神奈川県立生命の星・地球博物館 特別出版物 第2号 日本産ヒメバチ上科(膜翅目)の属への検索表. 奈川県立生命の星・地球博物館, 小田原. 524pp. ISBN: 9784910826011, https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1643173895521/simple/SPKPMNH_02_a.pdf
『日本産有剣ハチ類図鑑』
寺山守・須田博久. 2016. 日本産有剣ハチ類図鑑. 東海大学出版部, 平塚.ISBN: 9784486020752
日本産の有剣類、アリ類とハナバチ類を除く全種(847種)を掲載した。日本産のアリ類とハナバチ類を除く515種1000個体を超える標本写真を掲載した。本書では全グループで種までの検索表を提供し、各種の基本形態や生態、分布を解説した。本書の高次分類体系は、最新の分子系統解析によるものに準拠した。巻末で日本産種一覧や地域別、分類群別の文献目録を提供し、さらに生態写真も掲載した。
『紀伊國屋書店ホームページ』
【目次】
- 序 v
- はじめに-有剣類とカリバチ類とは- xii
- 有剣類の系統 xiii
- 有剣類の形態 xix
- 有剣類の生態 xxvi
- 本書の使い方 xxxi
- 上科の検索表 xxxv
- ミツバチ上科 Apoidea 寺山守,須田博久,高橋秀男,田埜正,南部敏明 1
- セナガアナバチ科 Ampulicidae 2
- アナバチ科 Sphecidae 3
- ギングチバチ科 Crabronidae 13
- クモバチ上科 Pompiloidea 寺山守 161
- アリバチ科 Mutillidae 寺山守,須田博久,室田忠男,田埜正 161
- アリバチモドキ科 Myrmosidae 寺山守 172
- ミコバチ科 Sapygidae 寺山守,須田博久 178
- クモバチ科 Pompilidae 清水晃,寺山守 178
- ツチバチ上科 Scolioidea 寺山守,長瀬博彦 248
- ツチバチ科 Scoliidae 248
- アゴバチ上科 Thynnoidea 寺山守 260
- アゴバチ科 Thynnidae 260
- コツチバチ上科 Tiphioidea 寺山守 264
- コツチバチ科 Tiphiidae 264
- スズメバチ上科 Vespoidea 山根正気,寺山守 290
- スズメバチ科 Vespidae 290
- セイボウ上科 Chryisidoidea 寺山守 335
- アリガタバチ科 Bethylidae 寺山守 335
- セイボウ科 Chrysididae 寺山守,須田博久,田埜正,室田忠男 388
- カマバチ科 Dryinidae 三田敏治 415
- アリモドキバチ科 Embolemidae 三田敏治,寺山守 450
- シロアリモドキヤドリバチ科 Sclerogibbidae 寺山守 454
- 標本写真図版
- ミツバチ上科 Apoidea 457
- セナガアナバチ科 Ampulicidae 457
- アナバチ科 Sphecidae 457
- ギングチバチ科 Crabronidae 461
- クモバチ上科 Pompiloidea 493
- アリバチ科 Mutillidae 493
- アリバチモドキ科 Myrmosidae 495
- クモバチ科 Pompilidae 495
- ミコバチ科 Sapygidae 509
- ツチバチ上科 Scolioidea 510
- ツチバチ科 Scoliidae 510
- アゴバチ上科 Thynnoidea 514
- アゴバチ科 Thynnidae 514
- コツチバチ上科 Tiphioidea 515
- コツチバチ科 Tiphiidae 515
- スズメバチ上科 Vespoidea 518
- スズメバチ科 Vespidae 518
- セイボウ上科 Chryisidoidea 535
- アリガタバチ科 Bethylidae 535
- セイボウ科 Chrysididae 537
- カマバチ科 Dryinidae 542
- アリモドキバチ科 Embolemidae 547
- ミツバチ上科 Apoidea 457
- 生態写真 548
- ミツバチ上科 Apoidea 548
- クモバチ上科 Pompiloidea 552
- ツチバチ上科 Scolioidea 554
- アゴバチ上科 Thynnoidea 555
- スズメバチ上科 Vespoidea 555
- セイボウ上科 Chryisidoidea 557
- 図版に掲載した標本のデータ 561
- 日本産有剣類種目録(アリ上科及びハナバチ類を除く) 577
- 図鑑,書籍,県別・地域別文献目録 619
- 引用・参考文献 647
- 和名索引 713
- 学名索引 720
『日本産ハナバチ図鑑』
多田内修・村尾竜起. 2014. 日本産ハナバチ図鑑. 文一総合出版, 東京. 479pp. ISBN: 9784829988428
植物の花粉媒介に大きな役割を果たし、生態系の健全性を測る指標としても注目されるハナバチ類。
生物多様性や生物間相互作用の重要性が浸透するなか、待望されていたその同定を支援するための図鑑が登場。
これまでほとんど知られていなかったその豊かな全貌と、同定のための形質を写真で紹介する。・日本産全種、6科389種を収録。一国産全種を網羅した写真図鑑の刊行は世界初!
『Amazon』
・最新の研究に基づく学名を採用。
・可能な限り、雌雄両方の標本写真を掲載。
・植物の花粉媒介を担う昆虫は、生態系の健全性を測る指標。その大きな一角を占めるハナバチ類の同定は環境調査に必須。
・同定の注目ポイントを5,000点を超える写真で紹介。類似種との相違点を比較しながら識別できる。
・大きさ、分布、発生時期に加え、訪花先の植物を記載。訪花姿勢を中心とした生態写真も多数収録。
【目次】
- はじめに 3
- 分類 7
- 生態 9
- 採集法 13
- 形態 17
- ミツバチ上科 Apoidea ハナバチ群 Apiformes の科までの検索 22
- ムカシハナバチ科 Colletidae 25
- コハナバチ科 Halictidae 155
- ケアシハナバチ科 Melittidae 263
- ハキリバチ科 Megachilidae 269
- ミツバチ科 Apidae 333
- 種の解説に掲載していない種 446
- 引用文献 447
- 学名索引 462
- 和名索引 466
- 訪花植物名索引 471
- 執筆者一覧 478
『神奈川県立生命の星・地球博物館 特別出版物 第1号 日本産ハナバチ類の同定の手引き(コハナバチ科の一部、ハキリバチ科、ミツバチ科キマダラハナバチ属を除く)』
渡辺恭平・長瀬博彦. 2022. 神奈川県立生命の星・地球博物館 特別出版物 第1号 日本産ハナバチ類の同定の手引き(コハナバチ科の一部、ハキリバチ科、ミツバチ科キマダラハナバチ属を除く). 神奈川県立生命の星・地球博物館, 小田原. 120pp. ISBN: 9784910826004, https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1643173895521/simple/SPKPMNH_01.pdf
『日本産マルハナバチ図鑑』
木野田君公・高見沢今朝雄・伊藤誠夫. 2013. 日本産マルハナバチ図鑑. 北海道大学出版会, 札幌. 191pp. ISBN: 9784832913967
日本産の全種・全亜種を生態写真と新鮮な標本写真で紹介!
[本書の特徴]
生態写真と新鮮な標本写真で紹介できるかぎり日本産全種・全亜種を載せたい/生態写真だけではものたりない/どんなところにどんな種類がすんでいるのかを知ってもらいたい/生態写真や全身の標本写真では種類がわかりにくいものは形態図や特徴的な部分のアップ写真があるとわかりやすい/種類を知るためだけの図鑑ではなくマルハナバチとつきあうための本にしたい/ナチュラリストから研究者までを対象とした広く深く長いおつきあいに耐えられる図鑑にしたい、こんな「夢の形」がここに結実!『北海道大学出版会ホームページ』
- 日本に産する5亜属15種・6亜種を収録したコンパクトながらも内容の充実した本格的な図鑑。
- 生態・生息環境写真約450枚と鮮明な標本写真約100枚を使って、日本のマルハナバチの世界をまるごと収録しました。
- 地域変異や個体変異などがひと目でわかるように、女王バチ、働きバチ、雄バチについて複数の地域標本を収録しました。
- どこで、いつごろ見られるかなどがひと目でわかるように、水平・垂直分布,営巣場所,活動時期、給餌法など関心の高い項目については、文章と共にイラストでも表示。
- よく似た種類については、毛の色や生え方などがひと目でわかるように写真やイラスト、比較表などを数多く使って見分ける箇所を具体的に表示しました。
- つきあう楽しさを伝えるために、巣の発見法や発掘法、飼育法、営巣期間及びコロニーサイズなどとっておきの情報を具体的に紹介しました。
- もっと詳しく知りたい方や研究者の方のためには、①下唇長・体長・頭幅、②磨縁部(マーラーエリア)、③側単眼周辺の点刻、④中脚基付節後端の形状、⑤交尾器、など各部位の形態について写真や図版を数多く使って、探求心や研究に役立てられるようにしました。
- 虫好きから専門家まで幅広く・長く・深く活用される図鑑です。
【目次】
- 北海道産マルハナバチ一覧
- 本州以南産マルハナバチ一覧
- 各種の解説
- ナガマルハナバチ亜属
- ナガマルハナバチ
- エゾナガマルハナバチ
- トラマルハナバチ
- エゾトラマルハナバチ
- ウスリーマルハナバチ
- ユーラシアマルハナバチ亜属
- ミヤママルハナバチ
- シュレンクマルハナバチ
- ニセハイイロマルハナバチ
- ハイイロマルハナバチ
- ホンシュウハイイロマルハナバチ
- ヤドリマルハナバチ亜属
- ニッポンヤドリマルハナバチ
- コマルハナバチ亜属
- コマルハナバチ
- エゾコマルハナバチ
- ツシマコマルハナバチ
- ヒメマルハナバチ
- アイヌヒメマルハナバチ
- アカマルハナバチ
- オオマルハナバチ亜属
- オオマルハナバチ
- エゾオオマルハナバチ
- ノサップマルハナバチ
- クロマルハナバチ
- セイヨオオマルハナバチ
- ナガマルハナバチ亜属
- よく似た種との見分け方
- 北海道産エゾトラ・ミヤマ・シュレンク♀働きバチの違い
- 北海道産エゾトラ・ミヤマ・シュレンク♂の違い
- 北海道産ニセハイイロ・ハイイロ♀働きバチ♂の違い
- 北海道産エゾコ・エゾオオ♀働き蜂の違い
- 北海道産アイヌヒメ♀・エゾオオ働きバチの違い
- 北海道産アイヌヒメ・エゾコ働きバチの違い
- 北海道産アイヌヒメ・エゾコ♂の違い
- 本州以南産ナガ・トラ・ウスリー♀働きバチ♂の違い
- 本州以南産コ・オオ♀働きバチの違い
- 本州以南産コ・クロ♀働きバチの違い
- 本州以南産オオ・クロ♂の違い
- 各部位の名称
- オス(♂)とメス(♀働きバチ)の見分け方
- 亜属の検索
- 各部位の形態
- 下唇長,体長,頭幅
- マーラーエリア♀働きバチ♂
- 側単眼周辺の点刻♀
- 中脚基付節先端の形状♀働きバチ
- 触角♀♂
- 上唇♀
- 交尾器♂
- マルハナバチとは
- ハチの進化
- 近縁のハチたち
- マルハナバチ族の特徴
- 日本産マルハナバチの類縁関係と起源
- マルハナバチの一生
- 花とマルハナバチの共進化
- マルハナバチの巣の発見法と発掘法
- マルハナバチの飼育法
- コロニーサイズ
- 主な参考文献
- 和名索引
『日本産アリ類図鑑』
寺山守・久保田敏・江口克之. 2014. 日本産アリ類図鑑. 朝倉書店, 東京. 278pp. ISBN: 9784254171563
もっとも身近な昆虫であると同時に、きわめて興味深い生態を持つ社会昆虫であるアリ類。本書は日本産アリ類10亜科59属295種すべてを、多数の標本写真と生態写真をもとに詳細に解説したアリ図鑑の決定版である。前半にカラー写真(全属の標本写真、および大部分の生態写真)を掲載、後半でそれぞれの分類、生態、分布、研究法、飼育法などを解説。また、同定のための検索表も付属する。昆虫、とりわけアリに関心を持つ学生、研究者、一般読者必携の書。
『朝倉出版ホームページ』
【目次】
- アリとは 1
- アリ類の系統と分類 3
- 日本のアリ類の生態 9
- 日本のアリ類の多様性と生物地理 21
- 検索と解説 29
- 高次分類体系 29
- 本書で取り扱った分布情報 30
- 隠蔽種を含む種の表記について 31
- 検索表 32
- アリ科 Family Formicidae 33
- ハリアリ型亜科群 Poneromorph subfamilies 36
- ノコギリハリアリ亜科 Amblyoponinae 36
- ノコギリハリアリ族 Amblyoponini 36
- ノコギリハリアリ属 Stigmatomma 36
- ノコギリハリアリ族 Amblyoponini 36
- カギバラアリ亜科 Proceratiinae 38
- ハナナガアリ族 Probolomyrmecini 39
- ハナナガアリ属 Probolomyrmex 39
- カギバラアリ族 Proceratiini 41
- ダルマアリ属 Discothyrea 41
- カギバラアリ属 Proceratium 42
- ハナナガアリ族 Probolomyrmecini 39
- ハリアリ亜科 Ponerinae 44
- ハリアリ族 Ponerini 47
- ヒメアギトアリ属 Anochetus 47
- オオハリアリ属 Brachyponera 48
- トゲズネハリアリ属 Cryptopone 50
- トゲオオハリアリ属 Diacamma 52
- ツシマハリアリ属 Ectomomyrmex 53
- ホンハリアリ属 Euponera 54
- ニセハリアリ属 Hypoponera 56
- ハシリハリアリ属 Leptogenys 61
- アギトアリ属 Odontomachus 61
- コガタハリアリ属 Parvaponera 63
- ハリアリ属 Ponera 63
- ハリアリ族 Ponerini 47
- ノコギリハリアリ亜科 Amblyoponinae 36
- サスライアリ型亜科群 Dorylomorph subfamilies 68
- クビレハリアリ亜科 Cerapachyinae 68
- クビレハリアリ族 Cerapachyini 68
- クビレハリアリ属 Cerapachys 68
- クビレハリアリ族 Cerapachyini 68
- クビレハリアリ亜科 Cerapachyinae 68
- ハリアリ型亜科群 Poneromorph subfamilies 36
その他論文
松浦誠. 2002. 絵とき検索シリーズ (12) 絵とき検索 日本産スズメバチ属. 昆虫と自然 37(8): 25-28.
ハエ目の同定文献
早川博文. 1990. 日本産アブ科雌成虫の分類-1-アブ属ウシアブ群、アカウシアブ群及びその関連種. 東北農業試験場研究資料 10: 35-49.
早川博文. 1990. 日本産アブ科雌成虫の分類-2-ヒゲナガサシアブ属及びゴマフアブ属. 東北農業試験場研究資料 10: 51-61. https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010460147.pdf
末吉昌宏. 2011. 日本産クチキバエ科の絵とき検索. はなあぶ 31: 1-18.
チョウ目の同定文献
『日本の鱗翅類 系統と多様性』
駒井古実・吉安裕・那須義次・斉藤寿久. 2011. 日本の鱗翅類 系統と多様性. 東海大学出版会, 秦野. 1305pp. ISBN: 9784486018568
鱗翅類の形態についての専門用語の平易な解説。チョウ・ガの系統や高次分類について多数の線画や写真を伴って詳しく解説する。寄主植物別にガ類の検索ができる。初めて図説された種を多数含む幼虫を中心に、卵、蛹、成虫を含めたカラー写真により図説する。
『Amazon』
【目次】
- 形態と生態(形態;鱗翅類の食性の多様性;鱗翅目性フェロモンの化学構造の多様性)
- 鱗翅類の系統と高次分類体系(鱗翅類の系統と高次分類体系の歴史;鱗翅類の分類体系)
- 日本産鱗翅類の多様性(日本の鱗翅類相;害虫としての鱗翅類;日本産鱗翅類の科(亜科)の検索 ほか)
『原色蝶類検索図鑑』
猪又敏男. 1990. 原色蝶類検索図鑑. 北隆館, 東京. 63+223pp. ISBN: 9784832600386
この蝶類検索図鑑は、蝶の羽の色・形・斑紋・翅脈や触角,体の特徴から、簡単に正しく蝶の種名が捜し出せる新タイプの図鑑である。1637点のカラー標本で日本産の蝶類全種に地方別の変異種まで、大型カラー写真で詳しく解説してあるので、採集したその場で、素早く蝶の名前を引き出せる。研究者、一般愛好者、デザイナーにも役立つ。
『北隆館ホームページ』
【目次】
- 序文 1
- はじめに 3
- 図鑑を読むにあたって 9
- この図鑑の使い方 13
- 蝶類の外部形態とその名称 14
- 検索図表
- セセリチョウ上科の科への検索 15
- アゲハチョウ上科の科への検索 21
- 図説 1
- アゲハチョウ科 Papilionidae 2~29
- シロチョウ科 Pieridae 30~52
- シジミチョウ科 Lycaenidae 54~114
- テングチョウ科 Libytheidae 114
- マダラチョウ科 Danaidae 116~118
- タテハチョウ科 Nymphalidae 120~162
- ジャノメチョウ科 Satyridae 164~184
- セセリチョウ科 Hesperiidae 186~206
- 和名索引 209
- 学名索引 215
- 参考文献 223
ヘビトンボ目の同定文献
下野谷豊一. 2015. 本州中部の福井県で発見されたクロスジヘビトンボの一新種. 三重県総合博物館研究紀要 62: 43-52.
http://www.nature.museum.city.fukui.fukui.jp/shuppan/kenpou/62/62-43-52.pdf
コウチュウ目の同定文献
『原色日本甲虫図鑑 1』
森本桂・林長閑. 1986. 原色日本甲虫図鑑 1. 保育社, 大阪. 450pp. ISBN: 9784586300686
その高い網羅性と甲虫を熟知した執筆陣によって、多くの方から高い評価をいただき続けてきた保育社の『原色日本甲虫図鑑』。詳しい図解と鮮やかな写真、解説もできるだけ簡潔かつ読者に伝わりやすく書かれている点が、ロングセラー商品となった所以です。2007年8月にケースのデザインを新しくし、増刷しました。(改訂はしておりません)
『Amazon』
『原色日本甲虫図鑑 1』は、自然界の中で、甲虫がどのようにして生き、種族を維持しているかを形態、生態学的に解説。系統、分類、分布などを史的背景(進化)という観点でまとめた最新の学説にもとづいた総論編。
【目次】
- 凡例 vi
- カラー図版 1
- 概説 (森本桂) 33
- 形態
- 成虫 (森本桂) 37
- 表面構造 (森本桂) 37
- 頭部 (森本桂) 38
- 胸部 (森本桂) 41
- 腹部 (森本桂) 49
- 消化系 (森本桂) 51
- 生殖系 (森本桂) 52
- 神経系 (森本桂) 53
- 呼吸系 (森本桂) 54
- 卵・幼虫・蛹 (林長閑) 65
- 卵 (林長閑) 65
- 幼虫 (林長閑) 65
- 蛹 (林長閑) 73
- 成虫 (森本桂) 37
- 生態―環境への適応,その多様性―
- 変態 (林長閑) 75
- 交尾と産卵 (林長閑) 77
- 交尾 (林長閑) 77
- 産卵 (林長閑) 78
- すみかと食物
- 地表と生活 (林長閑) 80
- 樹、草、花と生活 (林長閑) 84
- 枯れ木や朽ち木と生活 (林長閑) 88
- 菌類と生活 (林長閑) 92
- 樹液や発酵果実と生活 (林長閑) 95
- 水中生活 (佐藤正孝) 96
- 共生と寄生 (森本桂) 104
- 特殊環境と生活 (上野俊一) 113
- 天敵 (林長閑) 121
- 生活史戦略 (森本桂) 124
- カムフラージュ (黒澤良彦) 125
- ベーツ型擬態 (黒澤良彦) 126
- ミュラー型擬態 (黒澤良彦) 128
- 防衛 (森本桂) 130
- カブトムシの角とクワガタムシの大あご (森本桂) 134
- 産卵習性の進化 (森本桂) 135
- 系統と分類
- 甲虫の系統 (森本桂) 142
- 成虫による科までの検索表 (佐々治寛之) 165
- 幼虫による科までの検索表 (林長閑) 202
- 図版 1~113
- 分布
- 日本の甲虫相 (佐藤正孝) 219
- 地史的要因 (佐藤正孝) 219
- 日本の化石甲虫相 (佐藤正孝) 221
- 分布要素の類型 (佐藤正孝) 222
- 地理的変異と分化 (佐藤正孝) 226
- 移動と帰化 (森本桂) 231
- 日本の甲虫相 (佐藤正孝) 219
- 人間と甲虫
- 害虫
- 農林害虫 (森本桂) 234
- 乾材害虫 (林長閑) 238
- 食品害虫 (林長閑) 241
- 衣類害虫 (林長閑) 246
- 毒虫 (林長閑) 247
- 益虫
- 食虫性甲虫 (林長閑) 249
- 糞や死体処理 (林長閑) 249
- 雑草の駆除 (林長閑) 250
- 魚釣りの餌 (林長閑) 251
- 食物と飼料 (林長閑) 251
- 薬と毒薬 (林長閑) 251
- 害虫
- 日本産甲虫目分類表 (森本桂) 255
- 甲虫の系統と分類に関する主要文献目録 (森本桂) 269
- 索引 305
『原色日本甲虫図鑑 2』
上野俊一・黒沢良彦・佐藤正孝. 1985. 原色日本甲虫図鑑 2. 保育社, 大阪. 526pp. ISBN: 9784586300693
『原色日本甲虫図鑑 2』は、オサムシ科、ゲンゴロウ科、ハネカクシ科、クワガタムシ科、コガネムシ科などの約2000種2500固体を80図版に収め解説。ヤンバルテナガコガネなど、基準標本で図示されている種も多い。
『Amazon』
【目次】
- ナガヒラタムシ科 Cupedidae
- チビナガヒラタムシ科 Micromalthidae
- セスジムシ科 Rhysodidae
- ヒゲブトオサムシ科 Paussidae
- カワラゴミムシ科 Omophronidae
- ハンミョウ科 Cicindelidae
- オサムシ科 Carabidae
- クビボソゴミムシ科 Brachinidae
- コガシラミズムシ科 Haliplidae
- ムカシゲンゴロウ科 Phreatodytidae
- コツブゲンゴロウ科 Noteridae
- ゲンゴロウ科 Dytiscidae
- ミズスマシ科 Gyrinidae
- ツブミズムシ科 Torridincolidae
- ダルマガムシ科 Hydraenidae
- ホソガムシ科 Hydrochidae
- マルドロムシ科 Georissidae
- セスジガムシ科 Helophoridae
- ガムシ科 Hydrophilidae
- エンマムシダマシ科 Sphaeritidae
- エンマムシモドキ科 Synteliidae
- ホソエンマムシ科 Niponiidae
- エンマムシ科 Histeridae
- タマキノコムシ科 Leiodidae
- ヒゲブトチビシデムシ科 Colonidae
- ムクゲキノコムシ科 Ptiliidae
- ニセマキムシ科 Dasyceridae
- コケムシ科 Scydmaenidae
- チビシデムシ科 Catopidae
- シデムシ科 Silphidae
- デオキノコムシ科 Scaphidiidae
- ハネカクシ科 Staphylinidae
- アリヅカムシ科 Pselaphidae
- クワガタムシ科 Lucanidae
- クロツヤムシ科 Passalidae
- コブスジコガネ科 Trogidae
- コガネムシ科 Scarabaeidae
- タマキノコムシモドキ科 Clambidae
- マルハナノミダマシ科 Eucinetidae
- ナガハナノミダマシ科 Artematopidae
- マルハナノミ科 Helodidae
- マルトゲムシ科 Byrrhidae
- ヒラタドロムシ科 Psephenidae
- ダエンマルトゲムシ科 Chelonariidae
- チビドロムシ科 Limnichidae
- ナガドロムシ科 Heteroceridae
- ナガハナノミ科 Ptilodactylidae
- ドロムシ科 Dryopidae
- ヒメドロムシ科 Elmidae
『原色日本甲虫図鑑 3』
黒沢良彦・久松定成・佐々治寛之. 1985. 原色日本甲虫図鑑 3. 保育社, 大阪. 514pp. ISBN: 9784586300709
『原色日本甲虫図鑑 3』は、タマムシ科、コメツキムシ科、ホタル科、テントウムシ科、ゴミムシダマシ科、ハナノミ科ほか、同定のむずかしいグループのほとんどの種を収録。検索表や図で相違点を示し、同定の便宜をはかる。
『Amazon』
【目次】
- タマムシ科 Buprestidae
- ホソクシヒゲムシ科 Callirhipidae
- クシヒゲムシ科 Rhipiceridae
- ヒゲブトコメツキ科 Throscidae
- コメツキダマシ科 Eucnemidae
- コメツキムシ科 Elateridae
- ベニボタル科 Lycidae
- ジョウカイボン科 Cantharidae
- ホタルモドキ科 Omethidae
- ホタル科 Lampyridae
- カツオブシムシ科 Dermestidae
- マキムシモドキ科 Derodontidae
- ヒメトゲムシ科 Nesodendridae
- ホソマメムシ科 Thorictidae
- ヒラタキクイムシ科 Lyctidae
- ナガシンクイムシ科 Bostrychidae
- ヒョウホンムシ科 Ptinidae
- シバンムシ科 Anobiidae
- コクヌスト科 Trogossitidae
- カッコウムシ科 Cleridae
- ジョウカイモドキ科 Melyridae
- ツツシンクイムシ科 Lymexylonidae
- ヒメキノコムシ科 Sphindidae
- ネスイムシ科 Rhizophagidae
- タマキスイムシ科 Cybocephalidae
- ケシキスイ科 Nitidulidae
- ツツヒラタムシ科 Passandridae
- ヒラタムシ科 Cucujidae
- ホソヒラタムシ科 Silvanidae
- オオキスイムシ科 Helotidae
- キスイムシ科 Cryptophagidae
- ムクゲキスイムシ科 Biphyllidae
- キスイモドキ科 Byturidae
- コメツキモドキ科 Languriidae
- オオキノコムシ科 Erotylidae
- ミジンキスイムシ科 Propalticidae
- ミジンムシダマシ科 Discolomidae
- ミジンムシモドキ科 Phaenocephalidae
- カクホソカタムシ科 Cerylonidae
- ミジンムシ科 Corylophidae
- テントウムシダマシ科 Endomycidae
- テントウムシ科 Coccinellidae
- ヒメハナムシ科 Phalacridae
- ツヤヒメマキムシ科 Merophysiidae
- ヒメマキムシ科 Lathridiidae
- ツツキノコムシ科 Ciidae
- コキノコムシ科 Mycetophagidae
- ホソカタムシ科 Colydiidae
- ゴミムシダマシ科 Tenebrionidae
- ハムシダマシ科 Langriidae
- コブゴミムシダマシ科 Zopheridae
- タマムシモドキ科 Monommidae
- キノコムシダマシ科 Tetratomidae
- クチキムシ科 Alleculidae
- デバヒラタムシ科 Prostomidae
- クチキムシダマシ科 Elacatidae
- ハネカクシダマシ科 Inopeplidae
- ホソキカワムシ科 Mycteridae
- チビキカワムシ科 Salpingidae
- キカワムシ科 Pythidae
- ツヤキカワムシ科 Boridae
- クビナガムシ科 Cephaloidae
- アカハネムシ科 Pyrochroidae
- ヒラタナガクチキムシ科 Sychroidae
- ナガクチキムシ科 Melandryidae
- オオハナノミ科 Rhipiphoridae
- ハナノミ科 Mordellidae
- ハナノミダマシ科 Scraptiidae
- カミキリモドキ科 Oedemeridae
- ツチハンミョウ科 Meloidae
- アリモドキ科 Anthicidae
- ニセクビボソムシ科 Aderidae
『原色日本甲虫図鑑 4』
林匡夫・木元新作・森本桂. 1984. 原色日本甲虫図鑑 4. 保育社, 大阪. 438pp. ISBN: 9784586300716
「原色日本甲虫図鑑 4」は、カミキリムシ科、ハムシ科、オトシブミ科、ゾウムシ科、キクイムシ科などのほとんどの種を72図版に収録し、解説。農林業の害虫が数多く含まれており、それに関する記述もおこなった。
『Amazon』
【目次】
- カミキリムシ科 Cerambycidae
- ハムシ科 Chrysomelidae
- マメゾウムシ科 Bruchidae
- ヒゲナガゾウムシ科 Anthribidae
- オトシブミ科 Attelabidae
- ミツギリゾウムシ科 Brentidae
- ホソクチゾウムシ科 Apionidae
- ゾウムシ科 Curculionidae
- オサゾウムシ科 Rhynchophoridae
- ナガキクイムシ科 Platypodidae
- キクイムシ科 Scolytidae
『原色昆虫大圖鑑 第2巻 甲虫篇 新訂』
森本桂. 2007. 原色昆虫大圖鑑 第2巻 甲虫篇 新訂. 北隆館, 東京. 754pp. ISBN: 9784832608269
昭和34年初版発行の『原色昆虫大図鑑』(全3巻)を全面改訂。第II巻は日本産甲虫約4200種を掲載。和名・学名・分布などの記載を全面的に見直した他、科の検索表を新訂するなど、今日の分類基準にあわせ、40数年振りの全面改訂を行いました。
『北隆館ホームページ』
【目次】
- 新訂への序文 1~2
- 序 3~4
- 目次 5~6
- 概説 7~16
- 検索表 17~30
- 凡例 31
- 新訂版改稿者・分担表 32
- 図版 PLATE1~PLATE196
- 解説 1~445
- 和名索引 448~485
- 学名索引 486~526
- 解説
- ナガヒラタムシ科 Cupedidae【Pl.1】 1
- セスジムシ科 Rhysodidae【Pl.1】 1
- オサムシ科 Carabidae【Pl.1~27】 1~61
- コガシラミズムシ科 Haliplidae【Pl.28】 61~62
- ムカシゲンゴロウ科 Phreatodytidae【Pl.28】 62~63
- コツブゲンゴロウ科 Noteridae【Pl.28】 63~64
- ゲンゴロウ科 Dytiscidae【Pl.29~34】 64~77
- ミズスマシ科 Gyrinidae【Pl.34】 77~78
- ダルマガムシ科 Hydraenidae【Pl.35】 78~79
- セスジガムシ科 Helophoridae【Pl.35】 79
- ホソガムシ科 Hydrochidae【Pl.35】 79
- マルドロムシ科 Georyssidae【Pl.35】 79
- ガムシ科 Hydrophilidae【Pl.35~36】 79~83
- エンマムシダマシ科 Sphaeritidae【Pl.37】 83
- エンマムシモドキ科 Synteliidae【Pl.37】 83
- エンマムシ科 Histeridae【Pl.37~38】 83~88
- ムクゲキノコムシ科 Ptilildae【Pl.39】 88~89
- ニセマキムシ科 Dasyceridae【Pl.39】 89
- タマキノコムシ科 Leiodidae【Pl.39~40】 89~92
- ツヤシデムシ科 Agyrtidae【Pl.40】 92~93
- シデムシ科 Silphidae【Pl.41~42】 93~96
- デオキノコムシ科 Scaphidiidae【Pl.42~43】 96~98
- コケムシ科 Scydmaenidae【Pl.43】 98~99
- ハネカクシ科 Staphylinidae【Pl.44~54】 99~126
- クワガタムシ科 Lucanidae【Pl.55~58】 126~135
- クロツヤムシ科 Passalidae【Pl.58】 135
- センチコガネ科 Geotrupidae【Pl.59】 135~136
- ムネアカセンチコガネ科 Bolboceratidae【Pl.59】 136
- アツバコガネ科 Hybosoridae【Pl.59】 136
- コブスジコガネ科 Trogidae【Pl.59】 136~137
- アカマダラセンチコガネ科 Ochodaeidae【Pl.59】 137~138
- コガネムシ科 Scarabaeidae【Pl.60~72】 138~165
- タマキノコムシモドキ科 Clambidae【Pl.73】 165
- マルハナノミダマシ科 Eucinetidae【Pl.73】 165
- マルハナノミ科 Scirtidae【Pl.73】 165~166
- マルトゲムシ科 Byrrhidae【Pl.73】 166~167
- ナガハナノミ科 Ptilodactylidae【Pl.74】 167~169
- ヒラタドロムシ科 Psephenidae【Pl.75】 169~170
- ダエンマルトゲムシ科 Chelonariidae【Pl.75】 170
- チビドロムシ科 Limnichidae【Pl.75】 170~171
- ナガドロムシ科 Heteroceridae【Pl.75】 171
- ドロムシ科 Dryopidae【Pl.75】 171
- ヒメドロムシ科 Elmidae【Pl.75~76】 171~173
- タマムシ科 Buprestidae【Pl.77~81】 173~186
- ホソクシヒゲムシ科 Callirhipidae【Pl.82】 186
- クシヒゲムシ科 Rhipiceridae【Pl.82】 186
- ヒゲブトコメツキ科 Throscidae【Pl.82】 186
- コメツキムシ科 Elateridae【Pl.82~86】 186~198
- コメツキダマシ科 Eucnemidae【Pl.87】 198~201
- ホタルモドキ科 Omethidae【Pl.88】 201
- ホタル科 Lampyridae【Pl.88】 201~203
- ジョウカイボン科 Cantharidae【Pl.88~90】 203~206
- ベニボタル科 Lycidae【Pl.90~91】 206~209
- マキムシモドキ科 Derodontidae【Pl.91】 209
- ヒメトゲムシ科 Nosodendridae【Pl.91】 210
- カツオブシムシ科 Dermestidae【Pl.91~92】 210~212
- シバンムシ科 Anobiidae【Pl.92~93】 212~214
- ナガシンクイムシ科 Bostrychidae【Pl.93】 214~215
- コクヌスト科 Trogossitidae【Pl.94】 215~216
- カッコウムシ科 Cleridae【Pl.94~95】 216~219
- ジョウカイモドキ科 Melyridae【Pl.96】 219~221
- ホソキカワムシ科 Mycterdae【Pl.96】 221
- ツツシンクイムシ科 Lymexylidae【Pl.97】 221~222
- ヒラタムシ科 Cucujidae【Pl.97】 222
- チビヒラタムシ科 Laemophloeidae【Pl.97】 222~223
- ツツヒラタムシ科 Passandridae【Pl.97】 223
- ヒゲボソケシキスイ科 Kateretidae【Pl.98】 223
- ケシキスイ科 Nitidulidae【Pl.98~100】 223~231
- ネスイムシ科 Monotomidae【Pl.101】 231
- ヒメキノコムシ科 Sphindidae【Pl.101】 232
- ホソヒラタムシ科 Silvanidae【Pl.101】 232~233
- オオキスイムシ科 Helotidae【Pl.102】 233
- キスイムシ科 Cryptophagidae【Pl.102】 233~234
- ムクゲキスイムシ科 Biphyllidae【Pl.102】 234~235
- キスイモドキ科 Byturidae【Pl.102】 235
- オオキノコムシ科 Erotylidae【Pl.102~106】 235~244
- ヒメハナムシ科 Phalacridae【Pl.103】 237
- カクホソカタムシ科 Cerylonidae【Pl.103】 237~238
- テントウムシ科 Coccinellidae【Pl.107~109】 244~251
- テントウダマシ科 Endomychidae【Pl.110】 251~254
- ミジンムシ科 Corylophidae【Pl.111】 254
- ミジンムシダマシ科 Discolomidae【Pl.111】 254~255
- ヒメマキムシ科 Lathridiidae【Pl.111】 255
- ツツキノコムシ科 Ciidae【Pl.111】 255~256
- デバヒラタムシ科 Prostomidae【Pl.111】 256
- コキノコムシ科 Myeetophagidae【Pl.112】 256~258
- ホソカタムシ科 Colydlidae【Pl.112~113】 258~259
- ムキヒゲホソカタムシ科 Bothrideridae【Pl.113】 259~260
- ゴミムシダマシ科 Tenebrionidae【Pl.113~121】 260~277
- コブゴミムシダマシ科 Zopheridae【Pl.121】 277
- クチキムシ科 Alleculidae【Pl.121】 277~279
- ツヤキカワムシ科 Boridae【Pl.122】 279
- オオキノコモドキ科 Monommatidae【Pl.122】 279
- キカワムシ科 Pythidae【Pl.122】 279~280
- キノコムシダマシ科 Tetratomidae【Pl.122】 280
- ホソキカワムシ科 Mycteridae【Pl.122】 280~281
- チビキカワムシ科 Salpingidae【Pl.122】 281~282
- アリモドキ科 Anthicidae【Pl.122,135~136】 282, 307~310
- アカハネムシ科 Pyrochroidae【Pl.123】 282~283
- クビナガムシ科 Stenotrachelidae【Pl.123,126】 283~284, 289
- ヒラタナガクチキムシ科 Synchroidae【Pl.124】 284
- ナガクチキムシ科 Melandryidae【Pl.124~126】 284~289
- オオハナノミ科 Rhipiphoridae【Pl.126】 289~290
- ハナノミ科 Mordellidae【Pl.127~131】 290~299
- ハナノミダマシ科 Scraptiidae【P1.131】 299~301
- カミキリモドキ科 Oedemeridae【P1.132~133】 301~305
- ツチハンミョウ科 Meloidae【Pl.134】 305~307
- ニセクビボソムシ科 Aderidae【Pl.136】 310~311
- カミキリムシ科 Cerambycidae【Pl.137~162】 311~367
- ホソカミキリムシ科 Disteniidae【Pl.138】 314
- マメゾウムシ科 Bruchidae【Pl.163】 367~369
- ハムシ科 Chrysomelidae【Pl.163~177】 369~402
- ヒゲナガゾウムシ科 Anthribidae【Pl.178~179】 402~407
- チョッキリゾウムシ科 Rhynchitidae【Pl.180~181】 407~409
- オトシブミ科 Attelabidae【Pl.181】 409~411
- ミツギリゾウムシ科 Brentidae【Pl.182】 411~413
- ホソクチゾウムシ科 Apionidae【Pl.182】 413~414
- ゾウムシ科 Curculionidae【Pl.183~194】 414~439
- オサゾウムシ科 Rhynchophoridae【Pl.194】 438~439
- キクイムシ科 Scolytidae【Pl.195~196】 439~444
- ナガキクイムシ科 Platypodidae【Pl.196】 444~445
『日本産カミキリムシ』
大林延夫・新里達也. 2007. 日本産カミキリムシ. 東海大学出版会, 秦野. 818pp. ISBN: 9784486017417
『南陽堂書店』
- 2006年末までの最新の知見をふまえ、日本から記録されているカミキリムシ全946種(亜種を含む)を網羅した。このなかには、本書の旧版(日本産カミキリムシ検索図説)が刊行された1992年以降に・新たに記録されたすべてのタクサを含む。
- 新たにほぼ全種にわたる標本写真をカラーで掲載し、図解検索と合わせることにより、亜科や族、属、亜属レベルへの体系的な検索を経て、容易に種の同定ができる。
- 種の解説では、形態的特徴に加えて、成虫出現期、分布、寄主植物について記述したほか、、分類学的な変遷をたどることができる最新のシノニミックリストを新たに添付した。
- 別にこれまでに記録された寄主植物の一覧を加えたことにより、植物からも加害種の推定が可能である。
- カミキリムシを総合的に理解できるように、形態、生態、分布、系統、保全など、豊富な解説を掲載したほか、研究方法、生態写真の撮影法、採集法、標本作製法についても解説した。
- 大部分は未公開の、貴重な生態写真318種を掲載した。
- 本書は、カミキリムシの研究者、同好者だけでなく、応用昆虫学や森林生態学、さらに環境技術分野など多方面の関係者に必携の図解書である。
【目次】
- 概説(研究史;系統と分類;形態 ほか)
- 図解検索(ホソカミキリムシ科;カミキリムシ科)
- 種の解説(ホソカミキリムシ科;カミキリムシ科)
『日本産コガネムシ上科標準図鑑』
岡島秀治・荒谷邦雄. 2012. 日本産コガネムシ上科標準図鑑. 学研プラス, 東京. 444pp. ISBN: 9784054038479
コガネムシ上科は、クワガタムシ、カブトムシ、ハナムグリ、ふん虫などをふくむ、人気のあるグループである。種ごとの変化のみならず、亜種や地理的変異、しいては個体変異も大きく、バラエティにとんだ日本産コガネムシ上科を全部掲載した図鑑。
『学研出版サイト』
【目次】
- クワガタムシ科
- クロツヤムシ科
- コブスジコガネ科
- ムネアカセンチコガネ科
- センチコガネ科
- アカマダラセンチコガネ科
- マンマルコガネ科
- アツバコガネ科
- ヒゲブトハナムグリ科
- コガネムシ科
コウチュウ目のその他論文
春沢圭太郎. 1998. 絵とき検索シリーズ (7) 日本産モンシデムシ族の絵とき検索. 昆虫と自然 33(5): 32-36.
春沢圭太郎. 2002. 絵とき検索シリーズ (10) 絵とき検索 日本産モモブトシデムシ族. 昆虫と自然 37(5): 23-25.
八尋克郎. 1996. 日本産陸生オサムシ上科の科及び亜科への絵解き検索. 昆虫と自然 31(13): 34-40.
山崎一夫. 1996. 日本産アオゴミムシ族の絵とき検索. 昆虫と自然 31(3): 24–29.
中根猛彦. 1985. 日本の甲虫69 ヨツボシゴミムシ亜科2・スナハラゴミムシ亜科1. 昆虫と自然 20(9): 18-22.
中根猛彦. 1985. 日本の甲虫70 スナハラゴミムシ亜科2・アオゴミムシ亜科1. 昆虫と自然 20(11): 22-26.
中根猛彦. 1985. 日本の甲虫71 アオゴミムシ亜科2. 昆虫と自然 20(13): 15-19.
中根猛彦. 1986. 日本の甲虫72 アオゴミムシ亜科3. 昆虫と自然 21(2): 19-24.
中根猛彦. 1986. 日本の甲虫73 アオゴミムシ亜科4. 昆虫と自然 21(4): 18-24.
中根猛彦. 1986. 日本の甲虫74 アオゴミムシ亜科追加・ナガゴミムシ亜科7 ヒラタゴミムシ族1. 昆虫と自然 21(8): 23-25.
中根猛彦. 1986. 日本の甲虫75 ナガゴミムシ亜科8 ヒラタゴミムシ族2. 昆虫と自然 21(10): 19-22.
中根猛彦. 1986. 日本の甲虫76 ナガゴミムシ亜科9 ヒラタゴミムシ族3・ゴモクムシ亜科1. 昆虫と自然 21(12): 22-25.
中根猛彦. 1987. 日本の甲虫77 ゴモクムシ亜科2・クビナガゴミムシ亜科1. 昆虫と自然 22(1): 24-26.
中根猛彦. 1987. 日本の甲虫78 クビナガゴミムシ亜科2・スジバネゴミムシ亜科・ホソゴミムシ亜科1. 昆虫と自然 22(6): 16-18.
中根猛彦. 1987. 日本の甲虫79 トゲアトキリゴミムシ亜科・アトキリゴミムシ亜科1. 昆虫と自然 22(9): 25-29.
中根猛彦. 1987. 日本の甲虫80 アトキリゴミムシ亜科2. 昆虫と自然 22(11): 26-30.
大場信義. 2002. 絵とき検索シリーズ (7) 絵とき検索 ホタル科(日本産)(下). 昆虫と自然 37(2): 21-25.
大場信義. 2002. 絵とき検索シリーズ (8) 絵とき検索 ホタル科(日本産)(下). 昆虫と自然 37(3): 23-28.
奥島雄一. 2002. 絵とき検索シリーズ (9) 絵とき検索 日本産ジョウカイボン種群. 昆虫と自然 37(4): 26-28.
福富宏和. 2018. 日本産ナガタマムシ属 Agrilus の分類. 昆虫と自然 53(7): 5-8. https://ci.nii.ac.jp/naid/40021596213
今坂正一・林成多. 2011. 日本産ムシクソハムシ属の Chlamisus の絵解き検索. ホシザキグリーン財団研究報告 14: 179-187.
沢田佳久. 2002. 絵とき検索シリーズ (11) 絵とき検索 オトシブミ科(日本産). 昆虫と自然 37(6): 38-40.
森本桂. 2014. 甲虫の幼虫図鑑 ゾウムシ上科 (1) 分類に用いる形態. 昆虫と自然 49(14): 29-32.
森本桂. 2015. 甲虫の幼虫図鑑 ゾウムシ上科 (2) 科の検索表とヒゲナガゾウムシ科. 昆虫と自然 50(2): 21-25.
森本桂. 2015. 甲虫の幼虫図鑑 ゾウムシ上科 (3) オトシブミ科. 昆虫と自然 50(5): 34-39.
森本桂. 2015. 甲虫の幼虫図鑑 ゾウムシ上科 (4) チョッキリゾウムシ科. 昆虫と自然 50(8): 29-32.
森本桂. 2015. 甲虫の幼虫図鑑 ゾウムシ上科 (5) ゾウムシ科:高次分類. 昆虫と自然 50(11): 23-26.
大平仁夫. 1969. 日本のコメツキムシ(I). 昆虫と自然 4(10): 22-25.
大平仁夫. 1969. 日本のコメツキムシ(II). 昆虫と自然 4(11): 25-31.
大平仁夫. 1970. 日本のコメツキムシ(III). 昆虫と自然 5(2): 28-33.
大平仁夫. 1970. 日本のコメツキムシ(IV). 昆虫と自然 5(6): 15-17.
大平仁夫. 1970. 日本のコメツキムシ(V). 昆虫と自然 5(7): 19-24.
大平仁夫. 1970. 日本のコメツキムシ(VI). 昆虫と自然 5(9): 15-23.
大平仁夫. 1970. 日本のコメツキムシ(VII). 昆虫と自然 5(10): 19-24.
大平仁夫. 1971. 日本のコメツキムシ(VIII). 昆虫と自然 6(4): 21-27.
大平仁夫. 1971. 日本のコメツキムシ(IX). 昆虫と自然 6(9): 18-24.
大平仁夫. 1971. 日本のコメツキムシ(X). 昆虫と自然 6(11): 20-25.
大平仁夫. 1972. 日本のコメツキムシ(XI). 昆虫と自然 7(3): 18-22.
大平仁夫. 2017. 日本産コメツキムシ科幼虫の概要 (4). 昆虫と自然 52(13): 33-36.
大平仁夫. 2018. 日本産コメツキムシ科幼虫の概要 (5). 昆虫と自然 53(2): 35-37.
大平仁夫. 2018. 日本産コメツキムシ科幼虫の概要 (6). 昆虫と自然 53(4): 25-27.
大平仁夫. 2018. 日本産コメツキムシ科幼虫の概要 (7). 昆虫と自然 53(7): 27-30.
中根猛彦. 1955. 日本の甲虫(26) デオキノコムシ科1. 新昆虫 8(8): 53-56.
中根猛彦. 1955. 日本の甲虫(27).デオキノコムシ科2. 新昆虫8(9): 50-53.
中根猛彦. 1955. 日本の甲虫(28). デオキノコムシ科3. 新昆虫 8(10): 54-57.
久松定智. 2015. 日本の甲虫目概説 (1) 日本のヒゲボソケシキスイ科. 昆虫と自然 50(6): 25-27.
小川遼. 2015. 日本の甲虫目概説 (2) 日本産デオキノコムシ亜科概説. 昆虫と自然 50(9): 21-23.
久松定智. 2015. 日本の甲虫目概説 (3) 日本のケシキスイ科(コウチュウ目)(その1). 昆虫と自然 50(13): 30-33.
小川遼. 2016. 日本の甲虫目概説 (4) 日本産デオキノコムシ亜科 (1) カメノコデオキノコムシ属、スジデオキノコムシ属、アカバデオキノコムシ属. 昆虫と自然 51(1): 26-28.
小川遼. 2016. 日本の甲虫目概説(5) 日本産デオキノコムシ亜科(2) デオキノコムシ属(1) 昆虫と自然 51(4): 25-28.
久松定智. 2016. 日本の甲虫目概説 (6) 日本のケシキスイ科(コウチュウ目)(その2). 昆虫と自然 51(5): 26-28.
小川遼. 2016. 日本の甲虫目概説 (7) 日本産デオキノコムシ亜科 (3) デオキノコムシ属 (2). 昆虫と自然 51(9): 24-26.
久松定智. 2016. 日本の甲虫目概説 (8) 日本のケシキスイ科(コウチュウ目)(その3). 昆虫と自然 51(12): 24-26.
久松定智. 2017. 日本の甲虫目概説 (9) 日本のケシキスイ科(コウチュウ目)(その4). 昆虫と自然 52(1): 25-27.
久松定智. 2017. 日本の甲虫目概説 (10) 日本のケシキスイ科(コウチュウ目)(その5). 昆虫と自然 52(4): 23-26.